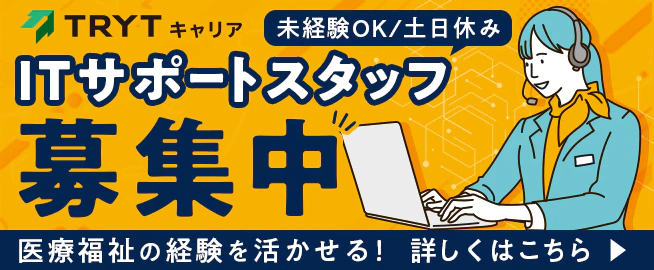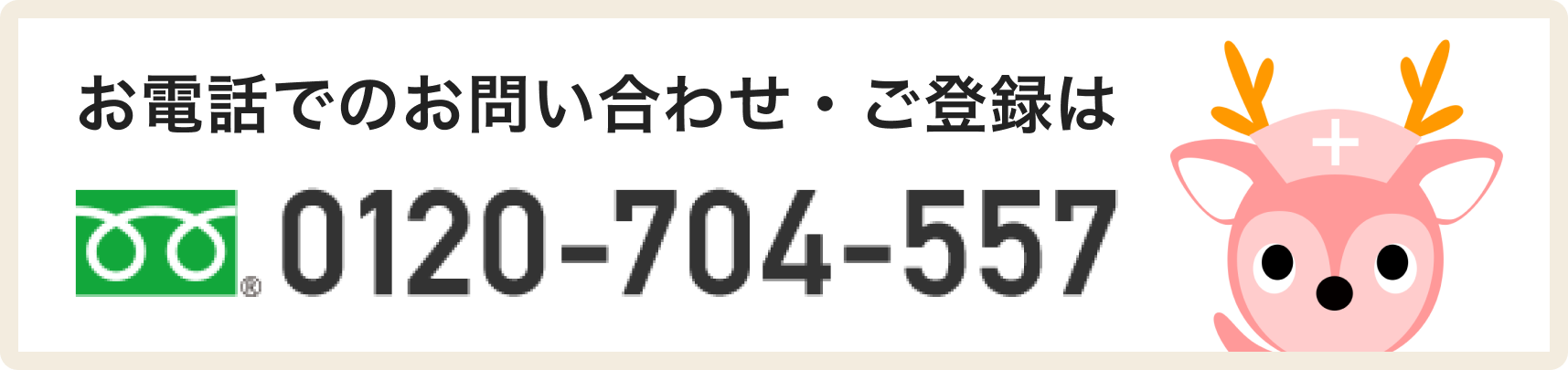医師国保に看護師が加入するデメリットとは?医師国保と国民健康保険の違い・加入方法を徹底解説!

日本国内に居住する国民は、何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。
国民健康保険や被用者保険、後期高齢者医療制度などさまざまな保険がありますが、その中の一つに、医師国保があります。
今回は、医師国保に看護師が加入するデメリットを解説します。
医師国保と国民健康保険の違いや加入方法を徹底解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。
医師国保とは?
医師国保の正式名称は、医師国民健康保険組合です。
各都道府県医師国保組合の規約によりさまざまな条件や加入手続きがありますが、基本的に、医師およびその家族と従業員・家族が加入対象です。
医師国保の運営組織
医師国保の運営を担っているのは、各都道府県の医師会です。
47都道府県すべてにありますので、全国各地で加入できます。
医師国保の加入条件
医師国保の加入条件は、各都道府県医師国保組合の規約により異なります。
今回は東京都の医師国保の加入条件を紹介します。
75歳未満の場合、下記の要件に該当する方が加入できます。
第1種組合員(医師)
・開業医、勤務医等
・東京都医師会会員である医師
・医療・福祉の事業または業務に従事していること
・規約に記載の住所地に住民票がある方
*新規加入時に既に法人事業所を開設している場合は加入できません。
*開業医の方の加入は地区医師会から東京都医師会へ加入されている方に限ります。
第2種組合員(従業員)
・看護師、医療事務等
・第1種組合員・第3種組合員に雇用されている従業員
・常勤または常勤に準ずる方
・規約に記載の住所地に住民票がある方
*東京都医師会会員の医師は、勤務医師であっても第1種組合員として加入していただきます。
家族
・組合員と住民票上同一世帯に属する方
・健康保険、共済組合、他の国保組合等に加入していない方
75歳以上の場合、下記の要件に該当する方が加入できます。
第3種組合員(医師)
・開業医、勤務医等
・東京都医師会会員である医師
・医療、福祉の事業または業務に従事していること
・規約に記載の住所地に住民票がある方
*新規加入時に既に法人事業所を開設している場合は加入できません。
*開業医の方の加入は地区医師会から東京都医師会へ加入されている方に限ります。
第4種組合員(従業員)
・看護師、医療事務等
・第1種組合員、第3種組合員に雇用されている従業員
・常勤または常勤に準ずる方
・規約に記載の住所地に住民票がある方
規約に記載の住所地とは、東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、および茨城県(取手市、利根町、龍ケ崎市、守谷市、常総市、つくばみらい市、つくば市、牛久市、阿見町、土浦市)です。
また、下記に該当する方は加入することができません。
・健康保険、船員保険および医療保険を行う共済組合等に加入している方
・他の国保組合に加入している方
・後期高齢被保険者の方(第3種・第4種組合員を除く)
・生活保護法の適用を受けている方
医師国保の保険料
医師国保の保険料は、各都道府県医師国保組合の規約により異なります。
今回は東京都の医師国保の保険料を紹介します。
東京都の医師国保の保険料は、以下の表の通りです。
種別 | 医療保険料 | 介護保険料(40歳~64歳の方) | 後期高齢者 組合員保険料 (75歳以上の方) | ||
① | ② | ①+② | |||
医療給付費 保険料 | 後期高齢者 支援金等 保険料 | 合計 | |||
第1種組合員 | 34500円 | 5000円 | 39500円 | 6000円 | ‐ |
第2種組合員 | 13500円 | 5000円 | 18500円 | 6000円 | ‐ |
第3種組合員 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1000円 |
第4種組合員 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 1000円 |
家族 (中学生~74歳) | 7500円 | 5000円 | 12500円 | 6000円 | ‐ |
家族 (未就学児~小学生) | 4500円 | 5000円 | 9500円 | ‐ | ‐ |
医師国保と国民健康保険の違い
続いては、医師国保と国民健康保険の違いを紹介します。
厚生労働省によると国民健康保険制度とは、以下の通りです。
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入されていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村(特別区を含む)が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されております。
持続可能な社会保障制度の確立を図るために制度の見直しが行われ、平成30年4月より、都道府県が財政運営の責任主体となる等、新たな国民健康保険制度となりました。
保険料
医師国保と国民健康保険の違いの1つ目は、保険料です。
国民健康保険は収入に応じて保険料が変わります。
一方、医師国保の場合は収入に関係なく一定という特徴があります。
ですので、年収が上がっても保険料負担が増加することがありません。
これは最も大きな違いとも言えます。
また、法人になると社会保険に加入することになり、医師国保に加入することはできません。
ですが、個人事業としてあらかじめ医師国保に加入していた場合には、法人化しても引き続き医師国保に加入することができます。
加入条件
医師国保と国民健康保険の違いの2つ目は、加入条件です。
厚生労働省によると、国民健康保険の加入資格は以下の通りです。
日本国内に住所を有する方であって、以下のいずれにも該当しない方は、国民健康保険の被保険者となります。
・ 他の医療保険(健康保険)に加入している方、その被扶養者
・ 生活保護を受けている方
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 短期滞在在留外国人の方 など
一方、医師国保に加入できるのは基本的に、医師およびその家族と従業員・家族のみです。
自家診療時の保険請求
医師国保と国民健康保険の違い3つ目は、自家診療時の保険請求です。
医師国保のメリット・デメリット
続いては、医師国保のメリット・デメリットを紹介します。
メリット・デメリットを比較し、最適な選択をしましょう。
医師国保のメリット
まずは、医師国保のメリットを紹介します。
今回は、保険料が収入にかかわらず定額であること、事業所の金銭的な負担がないこと、加入地域によって独自の助成金があることを解説します。
保険料が収入にかかわらず定額
医師国保のメリット1つ目は、保険料が収入にかかわらず定額であることです。
市町村国保の保険料は前年度の所得によって決まることから、かなり高額の保険料になる可能性がありますが、医師国保の保険料は一定です。
転職や勤続年数、勤務形態の変化があっても一定なので、国保より保険料が安くなる場合もあります。
事業所の金銭的な負担がない
医師国保のメリット2つ目は、事業所の金銭的な負担がないことです。
医師国保の保険料は被保険者本人の全額負担ですので、雇用側の事業所の金銭的な負担はありません。
加入地域によって独自の助成金がある
医師国保のメリット3つ目は、加入地域によって独自の助成金があることです。
今回は東京都の医師国保の独自の助成金を紹介します。
東京都の医師国保では、出産育児一時金を受け取れます。
出産育児一時金の条件や支給額などは、以下の通りです。
被保険者が、出産(妊娠4か月(85日)以上の流産・死産を含む)をされた場合は、出産育児一時金が支給されます。
なお、当組合では出産育児一時金に加えて、独自の付加給付があります。
産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産された場合は488,000円です。(合計518,000円)
多児の場合は人数分を支給します。
なお、被保険者が出産をされた場合は、産前産後期間相当分の保険料が免除されます。
当組合に加入する以前の健康保険が社会保険の本人で、1年以上の資格取得期間がある場合、退職後6か月以内の出産においては、以前に加入されていた社会保険から出産育児一時金が給付されます。
ただし、以前加入されていた社会保険に出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしなかった場合には、組合から出産育児一時金の支給をいたします。
その際、社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類をいただくことがありますのでご了承ください。
医師国保のデメリット
次に、医師国保のデメリットを紹介します。
今回は、収入が減少しても保険料は下がらないこと、世帯人数が増えると支払う保険料も増えること、各種手当や保険給付の種類が少ないこと、自家診療分の保険請求ができないことについて解説します。
収入が減少しても保険料は下がらない
医師国保のデメリット1つ目は、収入が減少しても保険料は下がらないことです。
保険料が一定であることはメリットでもありますが、収入が減少しても保険料は下がらないため、保険料が割高になる可能性もあります。
世帯人数が増えると支払う保険料も増える
医師国保のデメリット2つ目は、世帯人数が増えると支払う保険料も増えることです。
医師国保への加入は、国民健康保険法第6条で世帯単位の加入が義務付けられています。
同一世帯に区市町村国保との混在は認められませんので、世帯人数が増えると支払う保険料も増えてしまいます。
各種手当や保険給付の種類が少ない
医師国保のデメリット3つ目は、各種手当や保険給付の種類が少ないことです。
社会保険加入者に支給される各種手当や保険給付と比べ、医師国保は手当が少ない傾向にあります。
各種手当や保険給付の種類は各都道府県によって異なりますので、加入先の情報を確認しましょう。
自家診療分の保険請求ができない
医師国保のデメリット4つ目は、自家診療分の保険請求ができないことです。
医師が、自身や自身の家族、従業員に対し診察し治療を行うことを自家診療といいます。
医師国保に加入している場合には、原則自家診療分の保険請求ができません。
医師国保に加入している場合、この自家診療の保険請求は原則できない場合がほとんどです。
東京都医師国民健康保険組合では、自家診療について以下のように記載されています。
当組合の被保険者の方が、自己又は家族の所属する保険医療機関において療養を受けた場合、自家診療となり、請求および給付ができないことになっております。
当組合では、「組合規約」や「給付規程」でこれを規定しています。
なお、自家診療の請求が判明した場合は、その時点から3年間遡及し、該当の診療報酬明細書(調剤を含む)を返戻させていただきます。
自家診療に該当する例
①同一世帯に属する者についての診療
②所属する医療機関で受けた診療
③開設者が所属の医療機関で受けた診療
④これらの診療に付随する、処方箋による調剤レセプトや、診断書・同意書・証明書による療養費の申請(補装具、はり、きゅう、マッサージ等)
医師国保の加入方法・辞める方法
医師国保の加入方法や辞める方法は、各都道府県医師国保組合の規約により異なります。
今回は東京都の医師国保の加入方法・辞める方法を紹介します。
まず加入方法ですが、種別ごとに手続きが異なります。
第1種組合員が加入するときには、以下の書類が必要です。
必要な書類を組合まで郵送することで、加入できます。
①加入申込書 PDF
②個人番号(マイナンバー)の記載のある世帯全員が記載された住民票
3か月以内に発行された、個人番号や続柄等全て記載のもの
外国籍の方は、国籍・在留資格・在留期間に省略のないもの
※医師国保に加入しない方の個人番号は必要ありません。
③預金口座振替依頼書 PDF
④住民票上同一世帯で、医師国保に加入しない方の保険証のコピー
⑤個人番号(マイナンバー)確認書類のコピー
⑥ 身元確認書類のコピー
個人番号カード(表面)、運転免許証、パスポート等
⑦医療・福祉の事業または業務に従事していることの証明書
また、辞める方法も種別ごとに手続きが異なります。
第1種組合員が辞めるときには、以下の書類が必要です。
①資格喪失届 PDF
②保険証
③添付書類(下記の喪失事由に該当する添付書類)
まとめ
今回は、医師国保に看護師が加入するデメリットについて紹介しました。
加入方法や辞める方法は、種別ごとにさまざまな違いがあります。
医師国保と国民健康保険の違いを検討し、最適な選択をしましょう。