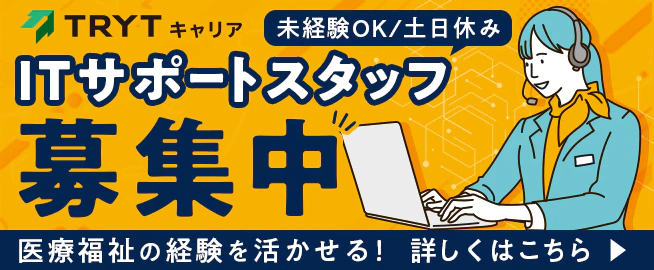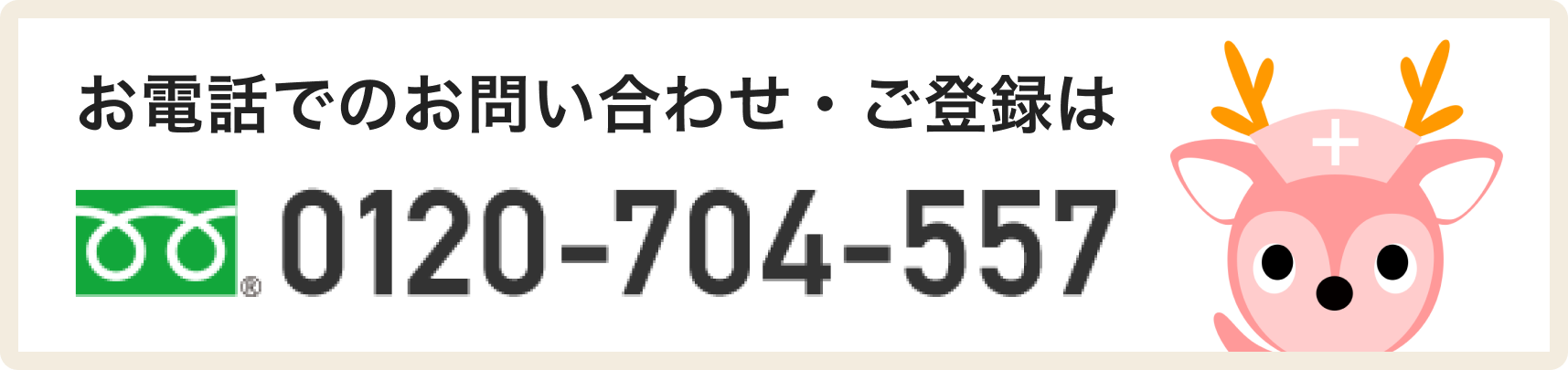褥瘡(じゅくそう)とは? 予防や要因|看護ケアまで徹底解説!

褥瘡って難しい言葉ですよね。褥瘡とは、簡単に言うと『とこずれ』の事です。医療現場では、褥瘡(じゅくそう)と呼ぶので覚えておきましょう。今回は、褥瘡ができる原因やケアについて解説していきます。ぜひ参考にしてくださいね。
褥 瘡とは?
褥瘡とは前述した通り簡単に言うと、とこずれの事です。とこずれと聞くと一気にわかりやすい用語になりますね。ではさっそく、褥瘡の定義や症状例について見ていきましょう。
褥瘡の定義とは?
まずは、褥瘡の定義をご紹介します。
一般社団法人 日本褥瘡学会のホームページによると、
“褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。”
(引用:一般社団法人 日本褥瘡学会http://www.jspu.org/jpn/patient/about.html)
と褥瘡について説明が明記されています。
一般社団法人 日本褥瘡学会のホームページによると、
“褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。”
(引用:一般社団法人 日本褥瘡学会http://www.jspu.org/jpn/patient/about.html)
と褥瘡について説明が明記されています。
褥瘡になるとどうなるの?
褥瘡になると、どうなるのでしょうか。
まずは、肌が赤くなります。その後、赤くなった部分が内出血を起こし水疱(水ぶくれ)やびらんが発生。初期・中期の褥瘡をそのまま放っておくと、皮膚が壊死していきます。
まずは、肌が赤くなります。その後、赤くなった部分が内出血を起こし水疱(水ぶくれ)やびらんが発生。初期・中期の褥瘡をそのまま放っておくと、皮膚が壊死していきます。
褥瘡になったら何科にかかるの?
褥瘡になったら、基本的には形成外科にかかりましょう。状況によっては皮膚科や内科、リハビリテーション科など様々な診療科で担当することになります。
褥瘡はなぜできるのか?
褥瘡はなぜできるのでしょうか?要因とできやすい場所についてご紹介します。
褥瘡の一番大きい要因とは?
褥瘡の一番大きい要因とは、体の一部が長時間圧迫されることです。特に寝たきりの患者で自ら身体を動かすことができない場合は、医師や看護師などの職員が患者の体位変換を定期的に行うことが大切です。
褥瘡はどのくらいでできる?
褥瘡は、圧迫されていた時間×圧力で重症度が決まります。状況によりますが、数時間で褥瘡は始まってしまいます。医療や介護の現場では、2〜3時間ごとの体位変換を目安にしましょう。
褥瘡ができやすい場所は?
褥瘡が特にできやすい場所があります。
それは、こちらです。
・仙骨部(臀部の正中部)
・坐骨部(座った際に臀部の骨が突出する部位)
・大転子部(大腿部の骨が突出する部位)
・踵部(足底)
・腸骨稜部(骨盤前部の骨が突出する部位)
大きい骨が突き出した箇所に褥瘡は出来やすいようです。
それは、こちらです。
・仙骨部(臀部の正中部)
・坐骨部(座った際に臀部の骨が突出する部位)
・大転子部(大腿部の骨が突出する部位)
・踵部(足底)
・腸骨稜部(骨盤前部の骨が突出する部位)
大きい骨が突き出した箇所に褥瘡は出来やすいようです。
褥瘡ができてしまったら・・・
褥瘡ができてしまったら、治療として軟膏やドレッシング材を使用することが多いです。
褥瘡には軟膏(ぬり薬)が効果的
褥瘡に塗る軟膏には種類があり、当然ながら成分によって効果が違います。
初期の褥瘡用、細菌が発生している褥瘡用、保湿成分の強い軟膏など、褥瘡の状態に適した軟膏を使いましょう。
初期の褥瘡用、細菌が発生している褥瘡用、保湿成分の強い軟膏など、褥瘡の状態に適した軟膏を使いましょう。
褥瘡に使うドレッシング材とは?
ドレッシング材とは、傷のある部分を覆う医療用の材料です。褥瘡部分を保護し、細菌の侵入を防ぎ、保湿する事で治療が望めます。ドレッシング材の交換の際に、傷口部分が破損しないようにする為には非固着性のドレッシング材を使いましょう。
褥瘡の皮膚の再生について
多くの褥瘡が治癒できるようになってきたものの、患者さんの体の状態や原因、治療の遅れなどから簡単には治癒できないこともあります。
褥瘡の皮膚の再生促進の為にも、初期の段階での発見と治療をスタートさせましょう。
褥瘡の皮膚の再生促進の為にも、初期の段階での発見と治療をスタートさせましょう。
褥瘡にならないような予防法って?
介護や医療の現場では、褥瘡にならないような予防が必要ですね。褥瘡の予防になる栄養と体位変換について説明していきましょう。
褥瘡と栄養の関係について
褥瘡の予防にも、褥瘡の治療にも低栄養の改善は必要です。
褥瘡の予防には、少なくとも 現在体重(kg)×25〜30Kcal の栄養素が1日に必要とされています。褥瘡の予防のため、良質のタンパク質や高エネルギー、ビタミンやミネラルが豊富な食事で栄養不足を解消させましょう。
引用:NPUAP/EPUAPガイドライン
https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/japan_quick-reference-guide-jan2016.pdf
褥瘡の予防には、少なくとも 現在体重(kg)×25〜30Kcal の栄養素が1日に必要とされています。褥瘡の予防のため、良質のタンパク質や高エネルギー、ビタミンやミネラルが豊富な食事で栄養不足を解消させましょう。
引用:NPUAP/EPUAPガイドライン
https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/japan_quick-reference-guide-jan2016.pdf
褥瘡と栄養~栄養不足の人は治りが悪い?
褥瘡がなかなか治らない患者さんの原因の一つに、栄養不足があります。栄養不足になるとむくみや血行が悪くなりますよね。さらに、筋肉量や脂肪組織が減少することで骨が突出し褥瘡の悪化につながります。
その為、タンパク質やエネルギー低栄養状態の患者に対しては、高タンパク質や高エネルギーのサプリメントによる補給を行うことが勧められています。
引用:日本褥瘡学会褥瘡予防・管理ガイドライン:http://www.jspu.org/jpn/info/pdf/guideline4.pdf
その為、タンパク質やエネルギー低栄養状態の患者に対しては、高タンパク質や高エネルギーのサプリメントによる補給を行うことが勧められています。
引用:日本褥瘡学会褥瘡予防・管理ガイドライン:http://www.jspu.org/jpn/info/pdf/guideline4.pdf
褥瘡 には定期的な体位変換が大切
健康な人は、褥瘡ができる前に痺れや痛みを感じて、部位を動かすので褥瘡になりにくいです。褥瘡になりやすいのは、長時間寝たきりの人や高齢者、何かしらの持病を持っている人と言えます。介護や医療の現場では、看護師の定期的な体位変換で褥瘡を防いであげましょう。
褥瘡(じゅくそう)とは? 正しく知って看護ケアをしよう
今回は、褥瘡について解説しました。
医療や介護の現場では、寝たきりの方が褥瘡にならないように2〜3時間おきに体位変換をしましょう。また、褥瘡になってしまったら早く治癒できるように必要なサポートをしていきましょうね。
医療や介護の現場では、寝たきりの方が褥瘡にならないように2〜3時間おきに体位変換をしましょう。また、褥瘡になってしまったら早く治癒できるように必要なサポートをしていきましょうね。