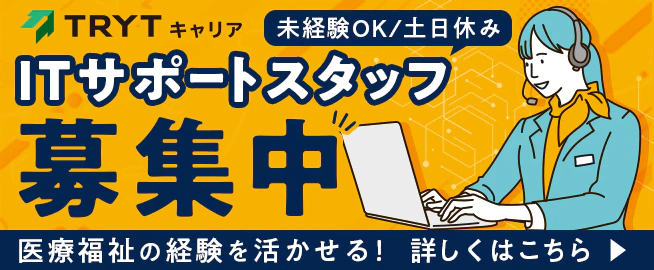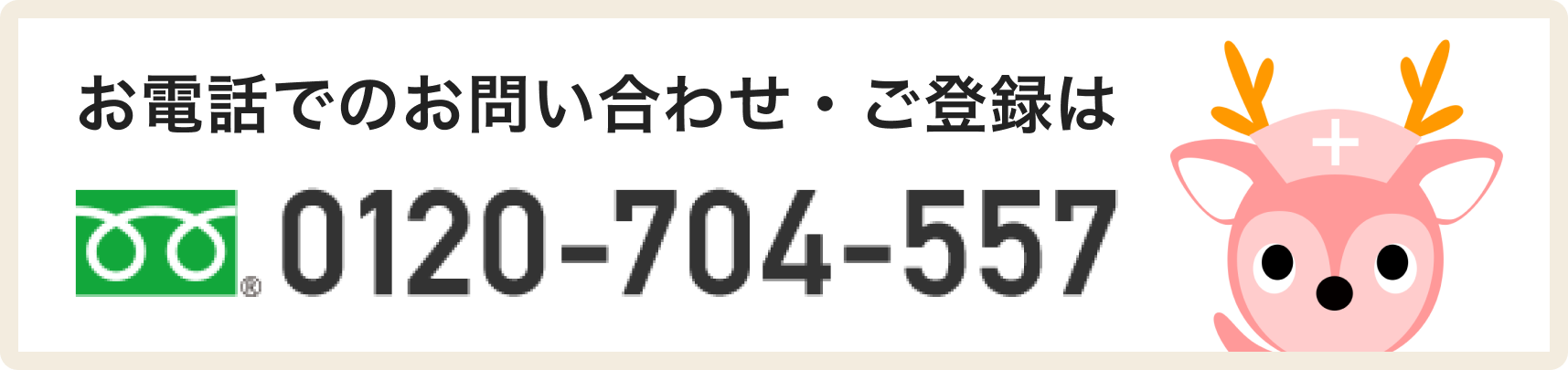看護や介護の現場で役立つボディメカニクスとは?原則やコツなどを簡単&わかりやすく解説!

看護や介護の仕事をしていると、患者さんの移乗などで腰を痛めてしまうことがありますよね。
厚生労働省によると、職場における腰痛は全国の業務上の疾病の約6割を占めているとのこと。 (参考:厚生労働省 腰痛予防対策について)
多くの方々が腰痛に悩まされていることが分かります。
今回は患者さんの移乗時などで腰痛予防に役立つ「ボディメカニクス」を紹介します。
ボディメカニクスのやり方、コツ、またボディメカニクス以外の腰痛予防も紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
厚生労働省によると、職場における腰痛は全国の業務上の疾病の約6割を占めているとのこと。 (参考:厚生労働省 腰痛予防対策について)
多くの方々が腰痛に悩まされていることが分かります。
今回は患者さんの移乗時などで腰痛予防に役立つ「ボディメカニクス」を紹介します。
ボディメカニクスのやり方、コツ、またボディメカニクス以外の腰痛予防も紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
ボディメカニクスとは
先程、職場における腰痛は全国の業務上の疾病の約6割を占めている と紹介しましたが、看護業界ではより多くの方が腰痛に悩まされています。
厚生労働省によると、保健衛生業では業務上疾病の全体の約8割が腰痛とのこと。
看護師の腰痛に関する調査では「腰痛があっても労災申請しない」と回答した人が約8割を占めました。(参考:厚生労働省 腰痛予防対策について)
これは看護師業界では腰痛が多いこと、腰痛が当たり前になってしまっている現状を表しています。深刻な腰痛問題を解決するために、ボディメカニクスとは何かをしっかりと押さえておきましょう。
厚生労働省によると、保健衛生業では業務上疾病の全体の約8割が腰痛とのこと。
看護師の腰痛に関する調査では「腰痛があっても労災申請しない」と回答した人が約8割を占めました。(参考:厚生労働省 腰痛予防対策について)
これは看護師業界では腰痛が多いこと、腰痛が当たり前になってしまっている現状を表しています。深刻な腰痛問題を解決するために、ボディメカニクスとは何かをしっかりと押さえておきましょう。
腰痛防止対策になる
ボディメカニクスは腰痛予防対策として効果的です。
厚生労働省は平成6年に「職場における腰痛予防対策指針」を発表しました。
改訂指針では、腰痛発生の要因は以下の4つであるとされています。
・動作要因
・環境要因
・個人的要因
・心理・社会的要因
医療の現場では被介護者を持ち上げる動作要因、一人で介護を行うことも多いという環境要因、女性が多い職場であり、筋肉量が低いという個人的要因、職務上の心理的負荷などの心理・社会的要因があると考えられます。
これらの要因から引き起こされる腰痛の対策方法として、ボディメカニクスを医療現場で役立てることが重要です。
(参考:厚生労働省 医療保険業の労働災害防止)
厚生労働省は平成6年に「職場における腰痛予防対策指針」を発表しました。
改訂指針では、腰痛発生の要因は以下の4つであるとされています。
・動作要因
・環境要因
・個人的要因
・心理・社会的要因
医療の現場では被介護者を持ち上げる動作要因、一人で介護を行うことも多いという環境要因、女性が多い職場であり、筋肉量が低いという個人的要因、職務上の心理的負荷などの心理・社会的要因があると考えられます。
これらの要因から引き起こされる腰痛の対策方法として、ボディメカニクスを医療現場で役立てることが重要です。
(参考:厚生労働省 医療保険業の労働災害防止)
介護しやすくなる
移乗や起き上がりの介護は、腰痛の原因になってしまうので苦手意識を持ってしまうことも。
ですがボディメカニクスを正しく活用することで、腰に負担をかけずに安定した介護を行うことができます。
また、ボディメカニクスを活用することで、介護する側はもちろん、介護される側にもメリットがあります。
余計な力を加えずに最小限の力で介護を行えるので、被介護者も安心感を得られます。
ですがボディメカニクスを正しく活用することで、腰に負担をかけずに安定した介護を行うことができます。
また、ボディメカニクスを活用することで、介護する側はもちろん、介護される側にもメリットがあります。
余計な力を加えずに最小限の力で介護を行えるので、被介護者も安心感を得られます。
ボディメカニクスの原則
ボディメカニクスを正しく行うためには、原理を十分に理解する必要があります。
ボディメカニクスの8原則を紹介します。
ボディメカニクスの8原則を紹介します。
①支持基底面積を広くとる
ボディメカニクスでは、支持基底面積を広くとることが重要です。
支持基底面積とは、体を支えるための基盤となる面積のこと。
重いものを持ち上げるときに、足を揃えて行うと、支持基底面積は狭くなります。
一方、足を十分に広げて支持基底面積を大きくして行うほうが安定し、重いものを持ち上げやすくなります。
患者さんを持ち上げる際には、肩幅程度に足を広げ、さらに前後に開くことで支持規定面積を広くとることができますよ。
支持基底面積とは、体を支えるための基盤となる面積のこと。
重いものを持ち上げるときに、足を揃えて行うと、支持基底面積は狭くなります。
一方、足を十分に広げて支持基底面積を大きくして行うほうが安定し、重いものを持ち上げやすくなります。
患者さんを持ち上げる際には、肩幅程度に足を広げ、さらに前後に開くことで支持規定面積を広くとることができますよ。
②重心を低くする
重心は低いほうが安定します。
患者さんを持ち上げる際にも、膝を曲げ重心を下げて行いましょう。
腰を曲げることでも重心を下げることができますが、膝から曲げることでより低く重心を保つことができます。
腰痛予防のためにも腰は曲げずに行いましょう。
また、先ほど紹介した支持基底面積の中に重心が入っていることで、より安定感を高めることができます。
患者さんを持ち上げる際にも、膝を曲げ重心を下げて行いましょう。
腰を曲げることでも重心を下げることができますが、膝から曲げることでより低く重心を保つことができます。
腰痛予防のためにも腰は曲げずに行いましょう。
また、先ほど紹介した支持基底面積の中に重心が入っていることで、より安定感を高めることができます。
③被介護者 と自分の重心を近づける
介護を受ける側と介護する側の重心を近づけることで、より安定した介護を行うことができます。
重いものを持つ際に自分の体から離して持つよりも、体に密着させたほうが安定することと同じ原理を利用します。
お互いの重心が近いと、力が伝わりやすくなり小さな力でも介護が行なえますので、腰痛予防はもちろん身体的な負担も最小限に抑えることができますよ。
介護の場面では、ベッドから車椅子に移乗する際に患者さんに抱きついてもらうような姿勢で行いましょう。
重いものを持つ際に自分の体から離して持つよりも、体に密着させたほうが安定することと同じ原理を利用します。
お互いの重心が近いと、力が伝わりやすくなり小さな力でも介護が行なえますので、腰痛予防はもちろん身体的な負担も最小限に抑えることができますよ。
介護の場面では、ベッドから車椅子に移乗する際に患者さんに抱きついてもらうような姿勢で行いましょう。
④被介護者の体を小さくまとめる
大きくて重いものよりも、小さくて重いもののほうが運びやすいですよね。介護する際にも、患者さんにできる限り体を小さくまとめてもらうと安定して行えます。
介護の場面では、ベッド上の仰臥位から起座位になってもらう際に役立ちます。
膝を曲げ、両腕をクロスし、体をコンパクトに縮めてもらいましょう。
こうすることで楽に介助を行えます。
介護の場面では、ベッド上の仰臥位から起座位になってもらう際に役立ちます。
膝を曲げ、両腕をクロスし、体をコンパクトに縮めてもらいましょう。
こうすることで楽に介助を行えます。
⑤重心の移動をスムーズにする
被介助者の重心移動は、水平移動を意識しスムーズに行いましょう。
持ち上げるような動作では、重さをダイレクトに感じてしまいます。
なるべく水平にスライドするような動作を心がけてください。
介護の場面ではベッドから車椅子移乗の際などに役立ちます。
上に持ち上げるような移乗ではなく、重心をスライドさせるように車椅子に座ってもらうことで最小限の力で行なえます。
持ち上げるような動作では、重さをダイレクトに感じてしまいます。
なるべく水平にスライドするような動作を心がけてください。
介護の場面ではベッドから車椅子移乗の際などに役立ちます。
上に持ち上げるような移乗ではなく、重心をスライドさせるように車椅子に座ってもらうことで最小限の力で行なえます。
⑥足先を動作の方向へ向け、手前に引く
押す力よりも引く力の方が、必要な力が小さくて済みます。
介護の場面では、ベッド上の移動では押すようにして行うのではなく、手前に引くようなイメージで行いましょう。
押す動作では腰に無駄な力が入り腰痛を引き起こしてしまう可能性があります。
介護の場面では、ベッド上の移動では押すようにして行うのではなく、手前に引くようなイメージで行いましょう。
押す動作では腰に無駄な力が入り腰痛を引き起こしてしまう可能性があります。
⑦身体全体を使い 、大きな筋群を使う
介護を行う際には、ついつい腕の力を使いがちですが、大きな筋群を使うことでより楽に介護できます。
腕の力だけではすぐに疲れてしまいますが、背中、足など体全体を使うよう意識することで安定感を高めることができます。特に背中や足には大きな筋群がありますので、積極的に使うようにしましょう。
腕の力だけではすぐに疲れてしまいますが、背中、足など体全体を使うよう意識することで安定感を高めることができます。特に背中や足には大きな筋群がありますので、積極的に使うようにしましょう。
⑧テコの原理を活用する
ボディメカニクスで重要となるのが、テコの原理 です。
テコの原理とは支点、力点、作用点を用いてものを動かすこと。
力が働く場所である力点と、力が作用する場所である作用点の間に支えとなる支点を置くことで、小さな力で動かすことができます。
介護の場面では、ベッド上仰臥位から起座位にする際に被介護者の臀部を支点にすることで楽に姿勢を変えることができますよ。
テコの原理とは支点、力点、作用点を用いてものを動かすこと。
力が働く場所である力点と、力が作用する場所である作用点の間に支えとなる支点を置くことで、小さな力で動かすことができます。
介護の場面では、ベッド上仰臥位から起座位にする際に被介護者の臀部を支点にすることで楽に姿勢を変えることができますよ。
ボディメカニクスのコツ
ボディメカニクスの原則を覚えたら、コツも押さえておきましょう。
いくつかのコツを押さえることで、より安定して介護を行うことができます。
今回は介護の際に大切な2つのポイントを紹介します。
いくつかのコツを押さえることで、より安定して介護を行うことができます。
今回は介護の際に大切な2つのポイントを紹介します。
被介護者に協力してもらうながら行う
ボディメカニクスを用いて介護を行う際には、被介護者の協力も必要不可欠です。
被介護者に協力してもらうことで、よりスムーズな介護が行なえます。
例えば、被介護者の体をなるべく小さくして移乗を行いたいときには、ご自身で体を動かしてもらいます。
また、重心を近づけるために介護者の体に抱きついてもらうなどの協力もお願いしてください。
被介護者ができる範囲で協力をお願いすることで、残存機能を活かすことにも繋がります。お互いの健康にとって大切なことですので、介護する際には協力をお願いしましょう。
被介護者に協力してもらうことで、よりスムーズな介護が行なえます。
例えば、被介護者の体をなるべく小さくして移乗を行いたいときには、ご自身で体を動かしてもらいます。
また、重心を近づけるために介護者の体に抱きついてもらうなどの協力もお願いしてください。
被介護者ができる範囲で協力をお願いすることで、残存機能を活かすことにも繋がります。お互いの健康にとって大切なことですので、介護する際には協力をお願いしましょう。
被介護者に声をかけながら行う
ボディメカニクスを用いて介護を行う際には、被介護者への声掛けが重要となります。
被介護者が、これからどのような動きをするのか分からないまま介護を受けると、恐怖心から余計に体に力が入ってしまいます。
どのような目的があって、どのような動きをするのか「就寝時間なので今からベットに移動します」「オムツを替えるので横になりましょう」などと予め伝えてから移乗などを行いましょう。
また、介護中も「体を起こします」「体を私側に向けます」など適宜声掛けを行います。
常にどのような介護を行っているのか声をかけることで、被介護者も安心しながら介護を受けることができますよ。
被介護者が、これからどのような動きをするのか分からないまま介護を受けると、恐怖心から余計に体に力が入ってしまいます。
どのような目的があって、どのような動きをするのか「就寝時間なので今からベットに移動します」「オムツを替えるので横になりましょう」などと予め伝えてから移乗などを行いましょう。
また、介護中も「体を起こします」「体を私側に向けます」など適宜声掛けを行います。
常にどのような介護を行っているのか声をかけることで、被介護者も安心しながら介護を受けることができますよ。
ボディメカニクスを活用するべき場面とは
ボディメカニクスは看護や介護のさまざまな場面で役立ちます。
ボディメカニクスが役立つ具体的な場面をいくつか紹介します。
ボディメカニクスが役立つ具体的な場面をいくつか紹介します。
移乗するとき
ベッド上から車椅子への移乗や、椅子への移乗などを行う際にボディメカニクスが役立ちます。
移乗をする際には、上に持ち上げずに水平移動を心がけましょう。
移乗をする際には、上に持ち上げずに水平移動を心がけましょう。
起き上がるとき
ベッドから起き上がるときにもボディメカニクスを活用しましょう。
被介護者を起き上がらせるのは、腰痛を起こしやすい介護ですが、重心移動に気をつけることで安全に行えます。
なるべく被介護者と介護者の重心を近づけて行い、介護者は支持基底面積を広く取り重心を下げて行いましょう。
被介護者を起き上がらせるのは、腰痛を起こしやすい介護ですが、重心移動に気をつけることで安全に行えます。
なるべく被介護者と介護者の重心を近づけて行い、介護者は支持基底面積を広く取り重心を下げて行いましょう。
体の向きを変えるとき
ベッド上で右仰臥位から左側臥位に変更するときなどにもボディメカニクスを活かすことができます。
被介護者には体を小さくまとめてもらい、手前に引く力を利用して体位変換を行います。
被介護者には体を小さくまとめてもらい、手前に引く力を利用して体位変換を行います。
立ち上がるとき
椅子やベッド上で座っている姿勢から立ち上がる時にも、ボディメカニクスが役立ちます。
被介護者を立ち上がらせるときには、介護者の体と密着させて行うことで、重心がブレずに安定して行えますよ。
また、立ち上がった先には手すりなどの介護用具があることが理想的です。
被介護者を立ち上がらせるときには、介護者の体と密着させて行うことで、重心がブレずに安定して行えますよ。
また、立ち上がった先には手すりなどの介護用具があることが理想的です。
座るとき
被介護者に座ってもらうときには、介護者も一緒に重心を下げます。
双方の重心が近くにある状態で座ってもらうことができるので、安定感を保って介護できますよ。
双方の重心が近くにある状態で座ってもらうことができるので、安定感を保って介護できますよ。
ボディメカニクス以外の負担軽減方法
これまでは、ボディメカニクスを活用した腰痛予防を紹介しました。
続いてはボディメカニクス以外の腰痛予防方法を見ていきましょう。
ボディメカニクスは腰痛予防として重要な対策ですが、ボディメカニクスだけでは腰痛を防ぐことは難しいとされています。
安全に介護を行うために、ボディメカニクス以外の腰痛対策方法も知っておきましょう。
続いてはボディメカニクス以外の腰痛予防方法を見ていきましょう。
ボディメカニクスは腰痛予防として重要な対策ですが、ボディメカニクスだけでは腰痛を防ぐことは難しいとされています。
安全に介護を行うために、ボディメカニクス以外の腰痛対策方法も知っておきましょう。
補助用具、福祉用具を活用する
被介護者を安全に介護するためには、補助用具や福祉用具を適切に使用する必要があります。
スライディングシートは比較的安価で、洗濯や消毒も可能な福祉用具です。スライディングシートは特別滑りやすい布製でできています。
ベッド上に敷いて患者さんを滑らせることで体位変換をしやすくしてくれます。
スライディングボードなども便利な福祉用具です。
ストレッチャーからベッドに移動する際にボードの上を滑らせるようにして利用したり、車椅子からベッドに移動する際に役立ちます。
また、移動式のリフトはより安定した移動を叶えてくれます。
自由に移動ができ、一台で多くの被介護者を移乗できるため、活躍の幅が広いのが特徴です。
スライディングシートは比較的安価で、洗濯や消毒も可能な福祉用具です。スライディングシートは特別滑りやすい布製でできています。
ベッド上に敷いて患者さんを滑らせることで体位変換をしやすくしてくれます。
スライディングボードなども便利な福祉用具です。
ストレッチャーからベッドに移動する際にボードの上を滑らせるようにして利用したり、車椅子からベッドに移動する際に役立ちます。
また、移動式のリフトはより安定した移動を叶えてくれます。
自由に移動ができ、一台で多くの被介護者を移乗できるため、活躍の幅が広いのが特徴です。
腰痛予防のストレッチをする
腰痛を予防するためには、腰痛予防体操の実施も効果的です。
厚生労働省が発表している「職場における腰痛予防対策指針 」では、腰痛予防体操はストレッチが重要であり、作業開始前、作業中、作業終了後、または疲労の状況に応じて適宜行うことが望ましいとされています。
腰痛予防のためには筋肉を伸ばした状態で行われる「静的なストレッチ」が効果的です。以下の点に留意しながら行いましょう。
厚生労働省が発表している「職場における腰痛予防対策指針 」では、腰痛予防体操はストレッチが重要であり、作業開始前、作業中、作業終了後、または疲労の状況に応じて適宜行うことが望ましいとされています。
腰痛予防のためには筋肉を伸ばした状態で行われる「静的なストレッチ」が効果的です。以下の点に留意しながら行いましょう。
- 息を止めずにゆっくりと吐きながら伸ばしていく
- 反動・はずみはつけない
- 伸ばす筋肉を意識する
- 張りを感じるが痛みのない程度まで伸ばす
- 20秒から30秒伸ばし続ける
- 筋肉を戻すときはゆっくりとじわじわ戻っていることを意識する
- 一度のストレッチで1回から3回ほど伸ばす
まとめ
今回は看護や介護の場面で活用されているボディメカニクスについて紹介しました。
ボディメカニクスを正しく活用することで、腰痛を予防しながら、被介護者に安心感を与える介護を行うことができます。
ボディメカニクスは腰痛予防対策として有効ですが、ボディメカニクスだけでは完全に腰痛を予防することはできません。
福祉用具の使用や、定期的なストレッチを行いながら腰痛の予防を行いましょう。
また、腰痛発生時には職場に報告し、適切な対処を行うことが重要です。
腰痛の慢性化や悪化を防ぎながら、無理のない安全な介護を実施しましょう。
ボディメカニクスを正しく活用することで、腰痛を予防しながら、被介護者に安心感を与える介護を行うことができます。
ボディメカニクスは腰痛予防対策として有効ですが、ボディメカニクスだけでは完全に腰痛を予防することはできません。
福祉用具の使用や、定期的なストレッチを行いながら腰痛の予防を行いましょう。
また、腰痛発生時には職場に報告し、適切な対処を行うことが重要です。
腰痛の慢性化や悪化を防ぎながら、無理のない安全な介護を実施しましょう。