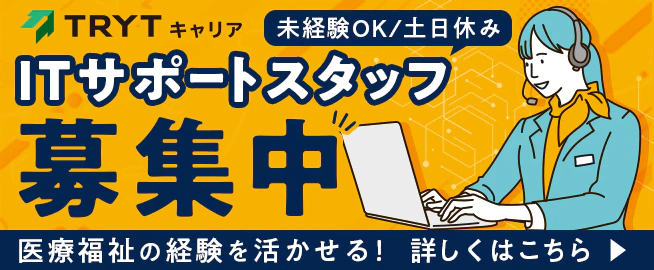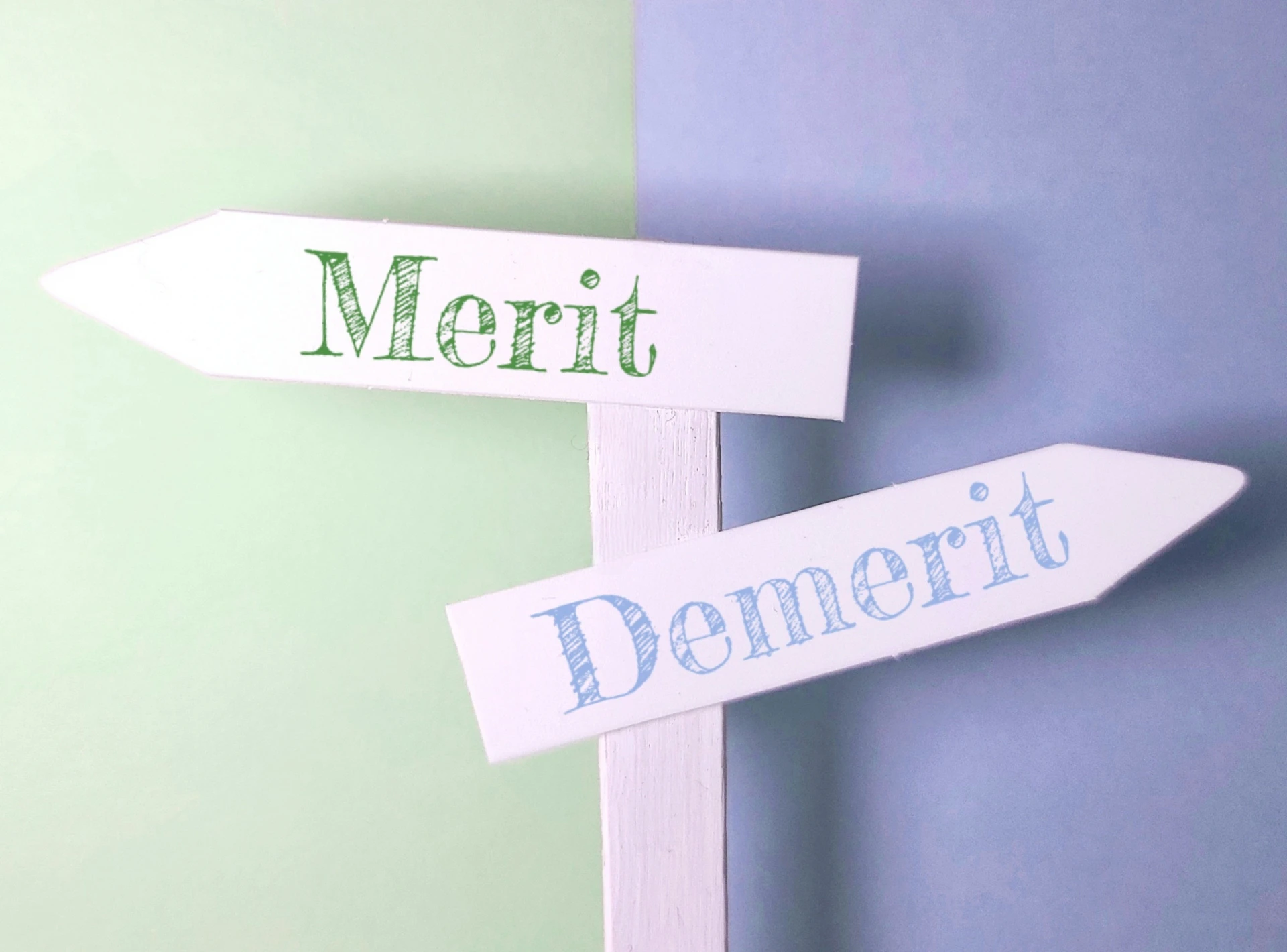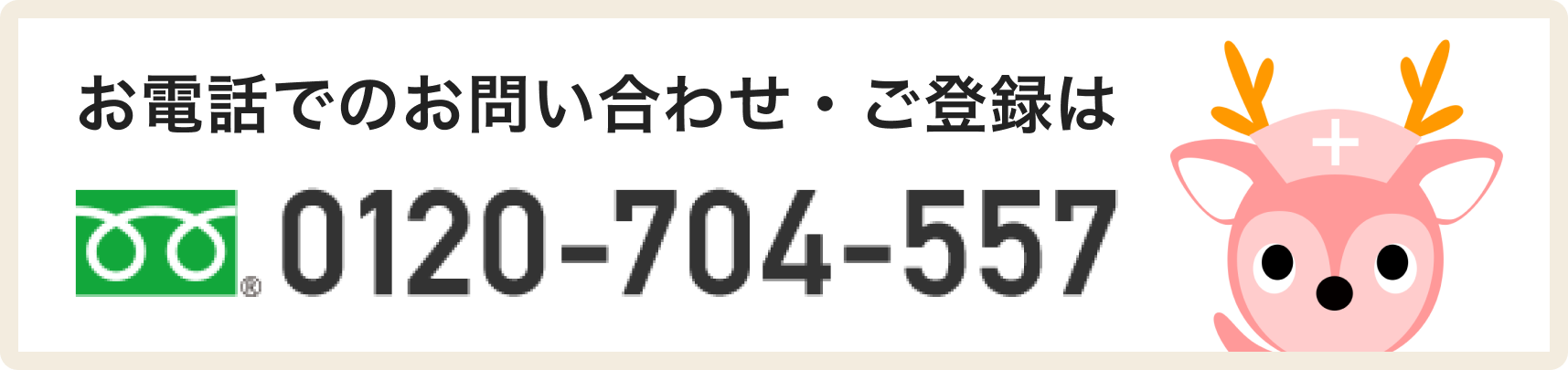在宅看護で大切なこと7つ!在宅看護のメリット・デメリット、訪問看護についてわかりやすく解説

在宅看護は高齢化が進んでいる日本において欠かせない医療提供体制です。
厚生労働省の調査によると、国民の60%以上が自宅での療養を望んでいるそうです。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
今回はニーズが高まっている在宅看護において、大切なことをまとめました。
在宅看護のメリットやデメリット、訪問看護の制度についてわかりやすく紹介します。
厚生労働省の調査によると、国民の60%以上が自宅での療養を望んでいるそうです。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
今回はニーズが高まっている在宅看護において、大切なことをまとめました。
在宅看護のメリットやデメリット、訪問看護の制度についてわかりやすく紹介します。
在宅看護の役割とは
在宅看護は、高齢化社会を支える重要な医療サービスです。
厚生労働省は看護の将来像として、以下の項目を掲げています。
・住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。
・認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、 認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
・ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口 は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
こうした将来像を実現するためには、在宅看護が重要となります。
地域に根づいた看護を行うためには、在宅での生活の支援や介護予防、療養を支える体制の充実が欠かせません。
厚生労働省は看護の将来像として、以下の項目を掲げています。
・住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの実現により、 重度な要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようになります。
・認知症は、超高齢社会の大きな不安要因。今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、 認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括ケアシステムの構築が重要です。
・ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口 は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差を生じています。 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や、都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
こうした将来像を実現するためには、在宅看護が重要となります。
地域に根づいた看護を行うためには、在宅での生活の支援や介護予防、療養を支える体制の充実が欠かせません。
在宅看護で大切なこと7つ
在宅にて看護を提供する上で大切なことを7つにまとめました。
コミュニケーション力
在宅看護は、その名の通り利用者さんの自宅に出向いて医療サービスを提供します。
利用者さんとの関係性は病棟での看護よりも、密なものとなります。
病棟で勤務する看護師は、日々入退院で変化する患者さんたちを大人数受け持つことになりますが、在宅看護では利用者さんが日常的に変わることはありません。
関わりもより深くなりますので、コミュニケーションスキルは必須です。
利用者さんのみならず、利用者さんのご家族ともコミュニケーションを行う必要があります。
現状どのような支援が必要なのか、困っていることはないか、今後どのような課題があるかを話し合いながら看護を行います。
利用者さんとの関係性は病棟での看護よりも、密なものとなります。
病棟で勤務する看護師は、日々入退院で変化する患者さんたちを大人数受け持つことになりますが、在宅看護では利用者さんが日常的に変わることはありません。
関わりもより深くなりますので、コミュニケーションスキルは必須です。
利用者さんのみならず、利用者さんのご家族ともコミュニケーションを行う必要があります。
現状どのような支援が必要なのか、困っていることはないか、今後どのような課題があるかを話し合いながら看護を行います。
多職種との連携
在宅看護では、多職種との連携も行う必要があります。
医師や介護職員、理学療法士や作業療法士と連携を取りながら在宅での看護を進めていきます。
さらに、在宅で医療を受ける利用者さんの多くは社会資源を利用されています。
社会資源の利用に関しては、ケアマネージャーやソーシャルワーカーさんの専門分野になるので、専門職の方々との連携も欠かせません。
さまざまな職種の方々と情報共有しながらケアプランを作成することで、より希望に寄り添った看護を提供することができます。
医師や介護職員、理学療法士や作業療法士と連携を取りながら在宅での看護を進めていきます。
さらに、在宅で医療を受ける利用者さんの多くは社会資源を利用されています。
社会資源の利用に関しては、ケアマネージャーやソーシャルワーカーさんの専門分野になるので、専門職の方々との連携も欠かせません。
さまざまな職種の方々と情報共有しながらケアプランを作成することで、より希望に寄り添った看護を提供することができます。
十分な看護技術
在宅看護では、基本的に看護師一人で訪問することが多く、一人で必要な看護を提供しなければいけません。
看護技術が不安だからと誰かを頼ることはできないので、十分な看護技術をマスターしておく必要があります。
基本的なバイタルサイン測定の技術はもちろん、体位変換や吸引などの身体的なケアや、入浴や洗髪の援助などの清潔ケアなどもあります。
実際の看護の内容は以下の通りです。
・病状観察
・本人の療養指導
・家族等の介護指導、支援
・介護職員によるたんの吸引等の実施状況の確認、支援
・栄養、食事の援助
・排泄の援助
・口腔ケア
・身体の清潔保持の管理、援助
・認知症、精神障害に対するケア
・嚥下訓練
・呼吸ケア、肺理学療法
・リハビリテーション
・社会資源の活用の支援
など。
医療処置に係る看護内容では以下のものがあります。
・気管内吸引
・その他の吸引
・在宅酸素療法の指導、援助
・膀胱内留置カテーテルの交換、管理
・ドレーンチューブの管理
・褥瘡の予防
・褥瘡の処置
・褥瘡以外の創傷部の処置
・経鼻経管栄養法の実施、管理
・胃瘻による経管栄養法の実施、管理
・人工肛門、人工膀胱の管理
・自己導尿の指導、管理
・気管カニューレの交換、管理
・人工呼吸器の管理
など
(参考:厚生労働省 介護サービス施設・事業所調査(平成28年9月))
在宅看護では限られた時間の中で看護を提供する必要がありますので、ケアに優先順位を付けて的確に行っていくスキルも求められるでしょう。
看護技術が不安だからと誰かを頼ることはできないので、十分な看護技術をマスターしておく必要があります。
基本的なバイタルサイン測定の技術はもちろん、体位変換や吸引などの身体的なケアや、入浴や洗髪の援助などの清潔ケアなどもあります。
実際の看護の内容は以下の通りです。
・病状観察
・本人の療養指導
・家族等の介護指導、支援
・介護職員によるたんの吸引等の実施状況の確認、支援
・栄養、食事の援助
・排泄の援助
・口腔ケア
・身体の清潔保持の管理、援助
・認知症、精神障害に対するケア
・嚥下訓練
・呼吸ケア、肺理学療法
・リハビリテーション
・社会資源の活用の支援
など。
医療処置に係る看護内容では以下のものがあります。
・気管内吸引
・その他の吸引
・在宅酸素療法の指導、援助
・膀胱内留置カテーテルの交換、管理
・ドレーンチューブの管理
・褥瘡の予防
・褥瘡の処置
・褥瘡以外の創傷部の処置
・経鼻経管栄養法の実施、管理
・胃瘻による経管栄養法の実施、管理
・人工肛門、人工膀胱の管理
・自己導尿の指導、管理
・気管カニューレの交換、管理
・人工呼吸器の管理
など
(参考:厚生労働省 介護サービス施設・事業所調査(平成28年9月))
在宅看護では限られた時間の中で看護を提供する必要がありますので、ケアに優先順位を付けて的確に行っていくスキルも求められるでしょう。
社会資源に関する知識
先程、社会資源に関してはケアマネージャーやソーシャルワーカーさんの専門分野だとお伝えしましたが、基本的な知識は看護師もしっかりと付けておく必要があります。
在宅看護と社会資源は切っても切れない関係です。
どのような保険を利用して、訪問看護を導入するのか。
どのような制度を利用して必要な在宅看護の器具を購入するのか、など社会資源の知識や情報が必要となる場面は多くあります。
利用者さんやご家族から、なにか使える社会資源はないかと質問されることもありますので、答えられるようにしておきましょう。
在宅看護と社会資源は切っても切れない関係です。
どのような保険を利用して、訪問看護を導入するのか。
どのような制度を利用して必要な在宅看護の器具を購入するのか、など社会資源の知識や情報が必要となる場面は多くあります。
利用者さんやご家族から、なにか使える社会資源はないかと質問されることもありますので、答えられるようにしておきましょう。
生活環境を把握するスキル
在宅での看護は、生活環境を整えることも重要な仕事内容です。
生活環境は一人一人異なります。
そして暮らし方はその人自身の生き様でもあります。
利用者さんの生活環境を十分に把握し、尊重しながら援助を行う必要があります。
といっても健康問題を引き起こすような生活環境は教育的な支援を行い、改善する必要があります。
まずは生活環境を十分に把握することが大切です。
生活環境は一人一人異なります。
そして暮らし方はその人自身の生き様でもあります。
利用者さんの生活環境を十分に把握し、尊重しながら援助を行う必要があります。
といっても健康問題を引き起こすような生活環境は教育的な支援を行い、改善する必要があります。
まずは生活環境を十分に把握することが大切です。
緊急時に対応できるスキル
在宅での看護は思いもよらないようなことが起こる可能性もあります。
利用者さんは健康状態に問題を抱えていますので、急変が起こることも考えられます。
在宅看護では、急変時も看護師一人で対応しなければいけない場合も。
急変時の救命措置の実施はもちろん、病院のように必要な設備が整っていないことが予想されますので、冷静な判断力も必要となります。
利用者さんは健康状態に問題を抱えていますので、急変が起こることも考えられます。
在宅看護では、急変時も看護師一人で対応しなければいけない場合も。
急変時の救命措置の実施はもちろん、病院のように必要な設備が整っていないことが予想されますので、冷静な判断力も必要となります。
車の運転免許
在宅看護では、利用者さんの家まで出向くのに自動車を利用する場合が多くあります。
中には自転車で移動することもありますが、基本は自動車での移動です。
普通自動車の運転免許を持っていることが訪問看護師の募集条件である場合も多いので、在宅看護を行いたいと考えている人は普通自動車の運転免許を取得しておくようにしましょう。
また、住宅街の細い道を通ることも予想されますので、運転に慣れておく必要もあります。
中には自転車で移動することもありますが、基本は自動車での移動です。
普通自動車の運転免許を持っていることが訪問看護師の募集条件である場合も多いので、在宅看護を行いたいと考えている人は普通自動車の運転免許を取得しておくようにしましょう。
また、住宅街の細い道を通ることも予想されますので、運転に慣れておく必要もあります。
在宅看護のメリット・デメリット
在宅看護を取り入れるメリット・デメリットを紹介します。
在宅看護のメリット
在宅看護の最大のメリットは、なんと言っても家で療養できること。
病院に入院しての療養は、慣れない環境下でストレスも大きなものとなります。
一方、慣れ親しんだ我が家では精神的な負担が少ない状況で治療に取り組むことができます。
また通院の頻度も減りますので、本人はもちろん家族の介護負担軽減になります。
病院に入院しての療養は、慣れない環境下でストレスも大きなものとなります。
一方、慣れ親しんだ我が家では精神的な負担が少ない状況で治療に取り組むことができます。
また通院の頻度も減りますので、本人はもちろん家族の介護負担軽減になります。
在宅看護のデメリット
在宅看護のデメリットは、高度な最先端医療を受けることが難しいという点です。
在宅では精密検査を行うことはできませんので、病院に出向いて検査を受ける必要があります。
最先端の治療はやはり、入院して環境が整った場所でないと受けることは難しいでしょう。
また、入院治療では身の回りの世話すべてを看護師や介護職員にお願いすることができますが、在宅での治療では家族が排泄の介助や清潔ケアを行う必要があります。
家族の介護負担は入院治療よりも増えてしまうのがデメリットだと言えるでしょう。
入院環境ではプロの医療従事者が24時間待機していますので、万が一の際も救命措置を受けられる安心感があります。
ですが、在宅では夜間など家族だけで看護している時間帯に急変が起こる可能性もあります。
在宅看護では万が一のときの安心感が少ない、というのも懸念点の一つです。
在宅では精密検査を行うことはできませんので、病院に出向いて検査を受ける必要があります。
最先端の治療はやはり、入院して環境が整った場所でないと受けることは難しいでしょう。
また、入院治療では身の回りの世話すべてを看護師や介護職員にお願いすることができますが、在宅での治療では家族が排泄の介助や清潔ケアを行う必要があります。
家族の介護負担は入院治療よりも増えてしまうのがデメリットだと言えるでしょう。
入院環境ではプロの医療従事者が24時間待機していますので、万が一の際も救命措置を受けられる安心感があります。
ですが、在宅では夜間など家族だけで看護している時間帯に急変が起こる可能性もあります。
在宅看護では万が一のときの安心感が少ない、というのも懸念点の一つです。
訪問看護とは
在宅で生活されている方に看護を提供することを、訪問看護と言います。
訪問看護では療養上のお世話を行ったり、診察の補助を行います。
訪問看護の現状や訪問看護師についてまとめました。
訪問看護では療養上のお世話を行ったり、診察の補助を行います。
訪問看護の現状や訪問看護師についてまとめました。
訪問看護の現状
日本では高齢化が進んでいます。
65歳以上の高齢者の数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎えると言われています。
その中でケアマネージャーの半数近くが意思との連携が取りづらいと感じており、医療や介護の連携は十分ではない状況だと言えるでしょう。
これらの現状を受け、平成24年補正予算や平成25年度予算によって、在宅医療の予算が見直されました。
また平成25年度からの5カ年の医療計画では、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」などの制度に関して明記が行われました。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
日本看護協会、全国訪問看護事業協会、公益財団法人日本訪問看護財団の3つの組織は合同で「訪問看護アクションプラン2025」というプランを策定しました。
訪問看護の量的拡大や機能拡大、質の向上、地域包括ケアへの対応などがまとめられています。
2025年までに現在の約3倍程度の訪問看護師が必要であるとされており、訪問看護師の安定的な確保が課題に挙げられています。
(参考:公益財団法人日本訪問看護財団 訪問看護アクションプラン2025)
65歳以上の高齢者の数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎えると言われています。
その中でケアマネージャーの半数近くが意思との連携が取りづらいと感じており、医療や介護の連携は十分ではない状況だと言えるでしょう。
これらの現状を受け、平成24年補正予算や平成25年度予算によって、在宅医療の予算が見直されました。
また平成25年度からの5カ年の医療計画では、新たに「在宅医療について達成すべき目標、医療連携体制」などの制度に関して明記が行われました。
(参考:厚生労働省 在宅医療・介護の推進について)
日本看護協会、全国訪問看護事業協会、公益財団法人日本訪問看護財団の3つの組織は合同で「訪問看護アクションプラン2025」というプランを策定しました。
訪問看護の量的拡大や機能拡大、質の向上、地域包括ケアへの対応などがまとめられています。
2025年までに現在の約3倍程度の訪問看護師が必要であるとされており、訪問看護師の安定的な確保が課題に挙げられています。
(参考:公益財団法人日本訪問看護財団 訪問看護アクションプラン2025)
訪問看護の対象患者
小児や40歳未満、要介護要支援者以外で訪問看護を利用している方は、約28.9万人います。これらの方は医療保険を利用して訪問看護を受けることができます。
要介護要支援者では55.4万人の方が訪問看護を利用されており、これらの方は介護保険を利用して訪問看護を受けることが可能です。
厚生労働大臣が定めている疾患の患者さんは、要支援要介護を受けている方でも医療保険を利用して訪問看護を受けることができます。
末期の悪性腫瘍や多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患などは厚生労働大臣が定めている疾患となります。
これらの疾患を抱えている方々も、訪問看護の対象です。
要介護要支援者では55.4万人の方が訪問看護を利用されており、これらの方は介護保険を利用して訪問看護を受けることが可能です。
厚生労働大臣が定めている疾患の患者さんは、要支援要介護を受けている方でも医療保険を利用して訪問看護を受けることができます。
末期の悪性腫瘍や多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患などは厚生労働大臣が定めている疾患となります。
これらの疾患を抱えている方々も、訪問看護の対象です。
訪問看護ステーションについて
訪問看護のサービスは病院や診療所、訪問看護ステーションが提供します。
平成31年時点で医療保険の訪問看護を行う訪問看護ステーションは10,783箇所。
介護保険の訪問看護を行う訪問看護ステーションは10,318箇所あります。
訪問看護ステーションの従事者数は、常勤で看護師約41,500人、准看護師約4,400人、理学療法士約9,400人、作業療法士約900人です。
どの職種も年々増加傾向にありますが、全従事者に占める看護職員の割合は71%であり、低下傾向にあります。
一方、1事業所あたりの従事者数は7.1人で、年々増加しています。
(参考:厚生労働省 訪問看護)
平成31年時点で医療保険の訪問看護を行う訪問看護ステーションは10,783箇所。
介護保険の訪問看護を行う訪問看護ステーションは10,318箇所あります。
訪問看護ステーションの従事者数は、常勤で看護師約41,500人、准看護師約4,400人、理学療法士約9,400人、作業療法士約900人です。
どの職種も年々増加傾向にありますが、全従事者に占める看護職員の割合は71%であり、低下傾向にあります。
一方、1事業所あたりの従事者数は7.1人で、年々増加しています。
(参考:厚生労働省 訪問看護)
訪問看護師になるには
訪問看護師になるには、前提として看護師資格が必要です。
正看護師または准看護師資格が必要となりますが、この他に必要な資格はありません。
訪問看護ステーションによっては、普通運転免許が必要となる場合もあります。
また、新卒で訪問看護師になることも可能ですが、3年以上病棟にて勤務経験があることを募集条件にしている事業所も多くあります。
看護ケア等のスキルを取得するには数年間病棟にて臨床経験を積むことが理想的だと言えるでしょう。
正看護師または准看護師資格が必要となりますが、この他に必要な資格はありません。
訪問看護ステーションによっては、普通運転免許が必要となる場合もあります。
また、新卒で訪問看護師になることも可能ですが、3年以上病棟にて勤務経験があることを募集条件にしている事業所も多くあります。
看護ケア等のスキルを取得するには数年間病棟にて臨床経験を積むことが理想的だと言えるでしょう。
訪問看護のアセスメント
看護の基本であるアセスメントですが、訪問看護では在宅でどのような生活を送りたいか、という利用者さんの希望に寄り添ったアセスメントが重要となります。
利用者さん本人の意志と、ご家族の意思の両方を情報収集しながらアセスメントを行いましょう。
また、訪問看護では看護師以外の職種もケアに関わっています。
介護職員やソーシャルワーカーとも情報を共有しケアプランを立てていくことがポイントとなります。
利用者さん本人の意志と、ご家族の意思の両方を情報収集しながらアセスメントを行いましょう。
また、訪問看護では看護師以外の職種もケアに関わっています。
介護職員やソーシャルワーカーとも情報を共有しケアプランを立てていくことがポイントとなります。
まとめ
今回は在宅看護についてまとめました。
在宅看護において重要なことは、利用者さんやご家族とコミュニケーションを取りながら、希望に寄り添った看護を行うことです。
在宅では最先端の医療や高度な検査等は実施できませんが、通院の手間や入院のストレスを軽減できます。
高齢化が進む日本で、よりニーズが高まっていく医療サービスだと言えるでしょう。
在宅看護において重要なことは、利用者さんやご家族とコミュニケーションを取りながら、希望に寄り添った看護を行うことです。
在宅では最先端の医療や高度な検査等は実施できませんが、通院の手間や入院のストレスを軽減できます。
高齢化が進む日本で、よりニーズが高まっていく医療サービスだと言えるでしょう。