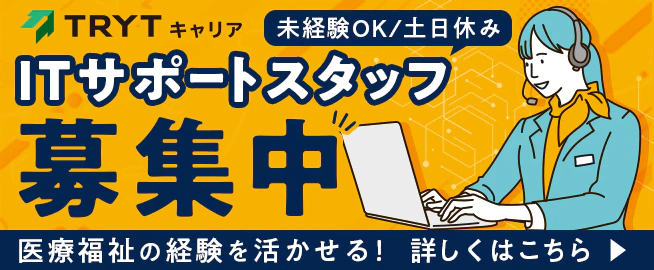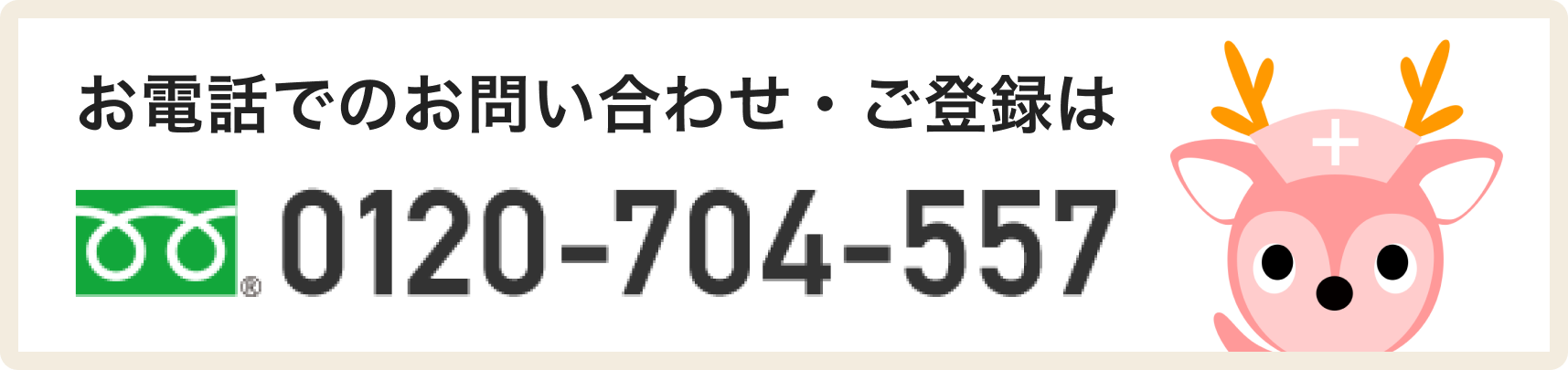多職種連携の必要性とは?看護師の役割について徹底解説!

一人の患者に対して、いくつもの専門職が連携して関わる多職種連携。
今、なぜ多職種連携が必要とされているのでしょうか?
今回は、多職種連携の中でも看護師に期待されている役割についてご紹介します。
今、なぜ多職種連携が必要とされているのでしょうか?
今回は、多職種連携の中でも看護師に期待されている役割についてご紹介します。
多職種連携とは?なぜ必要なのでしょうか
多職種連携は、なぜ必要なのでしょうか?
まずは、多職種連携の意味と多職種連携における看護師の必要性をみていきましょう。
まずは、多職種連携の意味と多職種連携における看護師の必要性をみていきましょう。
多職種連携とは
医療現場での多職種連携は、チーム医療とも言われています。
いろいろな職種の専門家が患者さまの情報を共有しながら、患者の目標が達成できるように努めることです。
いろいろな職種の専門家が患者さまの情報を共有しながら、患者の目標が達成できるように努めることです。
多職種連携における看護師の必要性
多職種で情報を共有しながら患者の目標を達成していくために、職種間の橋渡し役をすることが多いのが看護師です。看護師は患者と接する時間が他職種に比べて長く、患者と近い距離にいるため、多職種との連携をとる際のキーパーソンと言えます。
【多職種連携】看護師の役割を解説
では、具体的な看護師の役割をみていきましょう。
多職種連携・介護施設での看護師の役割とは
介護施設には、医師が常駐しないところもあるので、いざという時に判断を迫られるのは看護師です。入居者の担当介護士との連携、また入居者の通院している診療科の医師や他の専門家との情報共有が必要になってきます。普段から入居者の状況をしっかりと把握するよう心掛けましょう。
多職種連携・在宅(訪問看護)での看護師の役割とは
訪問看護を行う「訪問看護ステーション」は2021年4月の時点では13,303箇所あり、数は年々増えています。
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/r3-research.pdf
出典:一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和3年度 訪問看護ステーション数 調査結果」
事業所のサービスの内容も拡充していて、訪問看護師に求められる役割も増えてきました。
訪問看護師は介護職や医療の専門職との他職種連携はもちろんのこと、家族と専門職との橋渡しも行います。コミュニケーションを取り、調整を付けながら他職種との情報共有していくことが求められますね。
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/r3-research.pdf
出典:一般社団法人全国訪問看護事業協会「令和3年度 訪問看護ステーション数 調査結果」
事業所のサービスの内容も拡充していて、訪問看護師に求められる役割も増えてきました。
訪問看護師は介護職や医療の専門職との他職種連携はもちろんのこと、家族と専門職との橋渡しも行います。コミュニケーションを取り、調整を付けながら他職種との情報共有していくことが求められますね。
多職種連携・退院支援看護師の役割とは
退院支援看護師は、入院患者が退院できるようにサポートするのが仕事です。
病院から在宅へ戻る患者にとって、何が必要なのかを考えなければいけません。そのため医師や担当看護師、ソーシャルワーカーなどの専門職と退院前の情報共有が必要です。多職種連携によって患者の状況を判断しながら、退院前カンファレンスの実施の有無や社会的資源の調整にあたります。
病院から在宅へ戻る患者にとって、何が必要なのかを考えなければいけません。そのため医師や担当看護師、ソーシャルワーカーなどの専門職と退院前の情報共有が必要です。多職種連携によって患者の状況を判断しながら、退院前カンファレンスの実施の有無や社会的資源の調整にあたります。
多職種連携・高齢者が地域で暮らすための看護師の役割とは
2025年を目標に「地域包括ケアシステム」の構築を厚生労働省が進めています。
「地域包括ケアシステム」とは高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生を最期まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。地域で暮らす高齢者が、一貫した医療や介護の提供を受けるためには多職種連携が不可欠。看護師は高齢者に寄り添い、医療の提供を行いながら介護や各専門家への情報共有をしていきましょう。
「地域包括ケアシステム」とは高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生を最期まで続けることができるように地域内で助け合う体制のことです。地域で暮らす高齢者が、一貫した医療や介護の提供を受けるためには多職種連携が不可欠。看護師は高齢者に寄り添い、医療の提供を行いながら介護や各専門家への情報共有をしていきましょう。
多職種連携・精神科での看護師の役割とは
以前までは医師が中心であった精神科でも、多職種連携が進んできています。医師・保健師・看護師・精神保健福祉士・作業療法士・臨床心理士など患者と関わる専門職が互いに情報を共有することにより、より患者の状態を知り目標達成に向けて努めるようになりました。精神科での看護師は、各専門職の橋渡し役としても重要な役目を担っています。
他職種連携・ホスピスでの看護師の役割とは
ホスピスを受けられるところは、緩和ケア病棟・介護施設・自宅(訪問看護)などです。働く場所によって専門職の在籍は違ってきますが、緩和ケアの専門職や介護職など他職種との連携を取りながら患者の心身のケアをしていく必要があります。
看護師の役割を知って他の職種との連携を取りましょう
働く場所によって多少の違いはあるものの、看護師が多職種連携におけるキーパーソンであることは違いありません。それぞれの職種で行ったケアや治療の内容を共有し、トータルで患者をサポートできるようコミュニケーションを取りながら看護師として働きましょう!
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114473.pdf
参照:厚生労働省/多職種協働・地域連携
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114473.pdf
参照:厚生労働省/多職種協働・地域連携