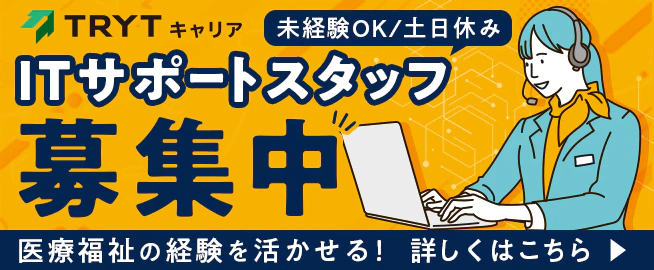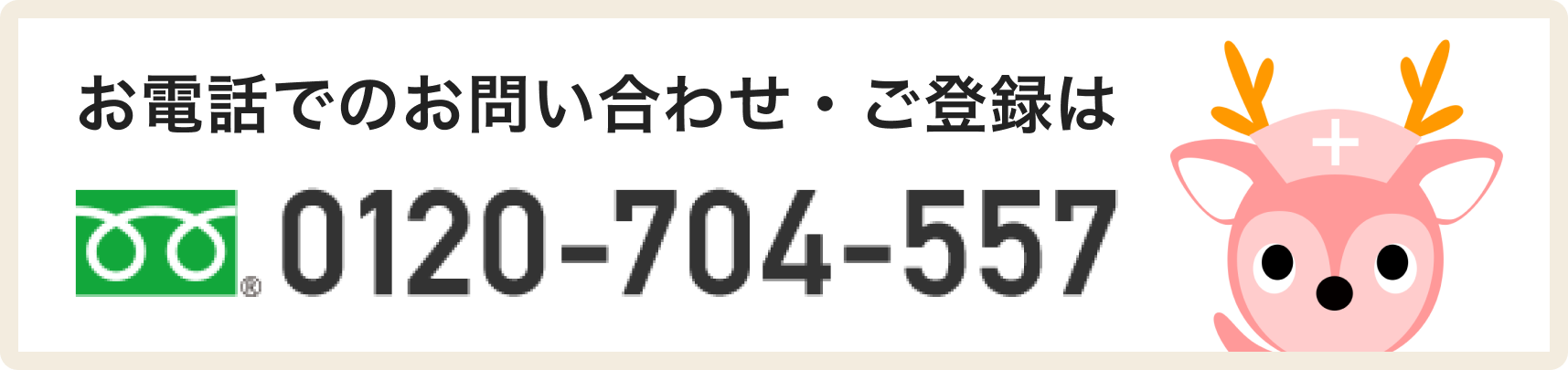難聴の患者さんの看護計画|コミュニケーションのコツを解説

難聴患者さんの看護計画やコミュニケーションの仕方にお悩みですか?
同じ難聴患者さんでも、一人ひとり看護目標や看護の仕方は違うものです。コミュニケーションの仕方についても、患者さんによって好き嫌いや得意不得意があります。
そこで今回は、難聴患者さんの看護計画を立てる際の注意点と、難聴患者さんとのコミュニケーションの仕方例をご紹介します。
難聴患者さんの看護にあたる看護師さんはぜひ参考にしてください。
難聴の患者さんの看護計画について
難聴の患者さんの看護計画については、いくつか注意が必要です。
高齢者の難聴患者の場合
高齢者の難聴患者さんの場合、成人の難聴患者さんとは治療方法や難聴への向き合い方も違ってきます。年齢と共に低下してきた筋力や視力、嚥下力、記憶力などさまざまな感覚が成人とは違うものです。高齢者の看護計画を作るのなら、まずは高齢者の特徴を知っておきましょう。
また、難聴を治癒させるという看護目標ではないことが多く、今持っている能力の維持が目標になる場合がほとんどです。看護計画を立てる際にも、この点を意識していきましょう。
急性期の難聴患者の場合
看護計画は、看護介入によって患者さんがどのような状態になることを期待するかを計画するものです。急性期の難聴患者さんの場合は、病気や症状を抑え症状が安定するまでの処置や治療を必要とします。症状によっては、投薬や手術をすることもあります。
急性期以外の難聴患者さんにも言えることですが、個別性のある看護計画を立てるためには具体的な看護の介入方法を取り入れることが大切です。患者さんの症状や徴候・関連因子や危険因子・なりゆきの3つのポイントから考え、看護計画を立てていきましょう。
難聴の患者さんとコミュニケーションをとるコツ
では、難聴の患者さんとコミュニケーションをとるコツについてご紹介しましょう。
・コミュニケーションの仕方を本人に確認する
患者さん本人に、どのようなコミュニケーションの仕方が望ましいか聞いてみましょう。
同じ症状や年齢の患者さんであっても、ラクにコミュニケーションを取れる方法は違います。もし、患者さん本人に直接聞けない場合には、家族や近しい人に普段のコミュニケーション方法を聞くのも良いかもしれません。
・なるべくはっきりと、ゆっくり話す
難聴の患者さんは、話す人の口の動きや表情から言葉を読み取ります。話す時はなるべくゆっくりと、口を大きく動かして話すことを心がけましょう。また、一文を長く話すのをやめ、短く区切りながら話すことを意識します。
・目線を合わせて話す
話している時に、患者さんと目線をしっかりと合わせましょう。口の動きを読むだけでなく、表情や目の動きなど全てが難聴患者さんに「伝える」ことに繋がります。対面で話す時だけでなく、車椅子やベッドに横たわっている患者さんと話す際にも、目線を合わせて話すようにしましょう。
・話すことを伝えてから話し始める
難聴患者さんは、相手の言葉を聞き取るのに必死です。伝えたいことが決まっている場合には、話す内容を事前に決めておきましょう。例えば、約束の日時/場所/お願いすることなど、伝える要所を単語に区切っておけば伝わりやすくなります。話す内容が決まっていないと、「あの〜」「えっと、そうそう」などの会話の接続詞が邪魔して、要件が伝わりにくくなるでしょう。
・身振りやジェスチャーも使う
難聴の患者さんとコミュニケーションを取る時には、身振りやジェスチャーも役立ちます。口の動きを見るよりも、ジェスチャーの方が時に状況を伝えやすいことも多いでしょう。表情や動きのあるコミュニケーションは、相手の心にも響きやすく精神的に不安な患者さんとの信頼関係の構築にもつながるかもしれません。
・筆談も取り入れてみる
より早く難聴患者さんへ要件を伝えるのなら筆談が良いでしょう。口の動きやジェスチャーで伝えるよりも、目で言葉を読めば瞬時に必要な情報を伝えることができます。ただし、要件が伝わっても筆談だけではコミュニケーション不足になるかもしれません。筆談中にも、表情を読むことや目を合わせて確認し合うように工夫しましょう。
難聴の患者さんとコミュニケーションをとりながら看護計画を立てよう
今回は、難聴の患者さんの看護計画作成の注意点と、難聴患者さんとのコミュニケーションの仕方をご紹介しました。
看護計画を立てる際には、難聴という症状でひとくくりにするのではなく、患者さんの性格や特性を理解しながら個別性のある看護計画を立案しましょう。また、難聴患者さんとのコミュニケーションには、さまざまな方法があります。今回ご紹介した方法以外にも、自分が看護する患者さんに最適な方法を見つけながら、信頼関係を築いていきましょう!