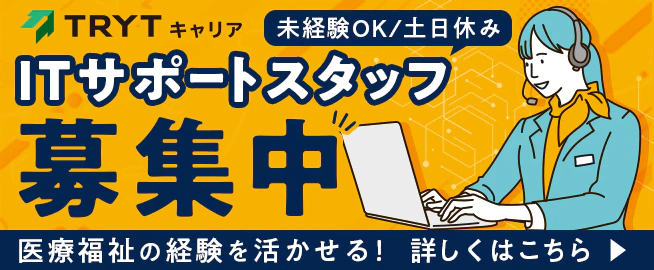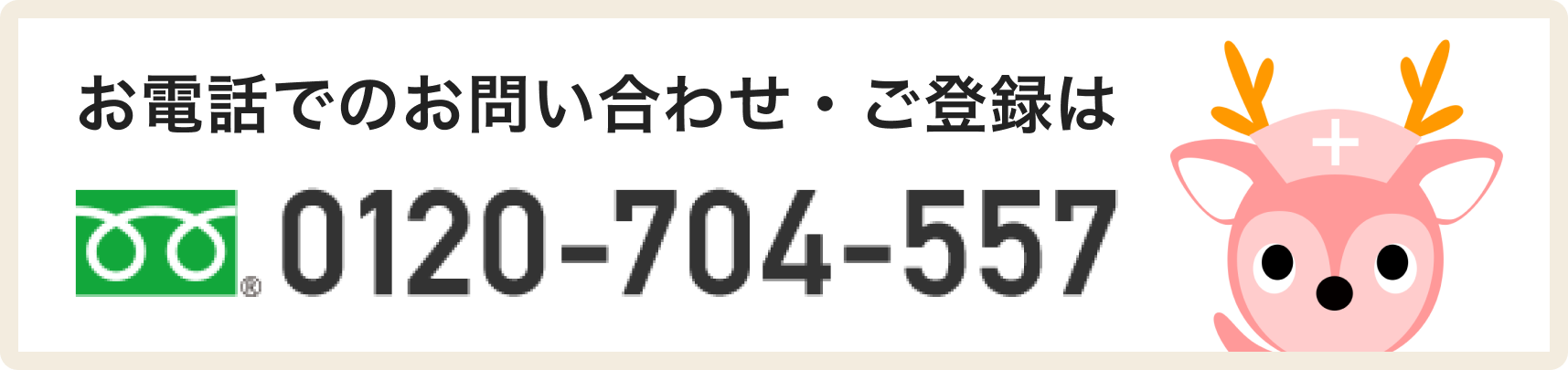看護師に長期休みはある?看護師の休暇・有給休暇に関する疑問・長期休みの過ごし方を徹底解説

「看護師は激務だ」「看護師は休みが取れない」というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、看護師に長期休みはあるのかを紹介します。
看護師の休暇・有給休暇に関する疑問・長期休みの過ごし方を徹底解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。
看護師に長期休みはある?
さっそくですが、看護師に長期休みはあるのでしょうか。
結論から申しますと、看護師にも一般職同様に長期休暇はあります。
ですが、長期休暇を取るタイミングや期間には制限があります。
平均年間休暇や有給所得率について、次章以降でより詳しく紹介します。
看護師の平均年間休暇
厚生労働省が発表している令和2年就労条件総合調査によると、看護師の平均年間休暇は、112.4日です。(医療、福祉業界の平均年間休日総数)
看護師の有給所得率
次に、看護師の有給所得率を紹介します。
厚生労働省が発表している令和2年就労条件総合調査によると、看護師の有給所得率は、53.4%です。(医療、福祉業界の平均有給所得率)
4週8休とは
休日や休暇についてよく聞くワード、4週8休とはどのような制度なのでしょうか。
4週8休とは、週5日勤務、休日2日。所定労働時間40時間の割り振りは、1日8時間(休憩を除く実働時間)×5日の働き方です。
また、4週7休とは、4週7休=週6日勤務(1日は半日勤)、休日1日。平日7時間45分(休憩を除く実働時間)× 5日+半日勤務日3時間45分の働き方です。
4週6休とは、4週6休(隔週週休2日)。半日勤務を2週分まとめて1日勤務とする代わりに隔週の1日休日を設定。交代制勤務では週末が必ずしも所定の休日になりませんが、勤務日数の考え方は同じです。
看護師の休暇・有給休暇について
続いては、看護師の休暇・有給休暇について紹介します。
有給休暇取得への道、有給が取れない場合や有給を取る理由、パートの有給について解説します。
有給休暇取得への道
まずは、看護師の休暇・有給休暇について、公益社団法人日本看護協会のホームページに記載されている「有給休暇取得への道」を紹介します。
「有給休暇が取れない」「長期休暇が欲しい」と多くの看護職から声が寄せられています。
「時間外勤務、夜勤・交代制勤務等緊急実態調査」(2008年)からも、看護職は日々の仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねないリスクがあることが明らかになっています。心身の健康が保たれてこそ、安心・安全で質の高いケア提供が可能となります。できることから職場で取り組んでみませんか。
・「個人別年次有給休暇取得計画表」の作成
年度の初めに個人ごとに作成します。作成にあたっては各人の取得希望時期を聞いた上で、必要があれば部署ごとに取得時期を調整します。その際、労使協定による「年次有給休暇の計画的付与制度」を活用して、休暇取得日が集中するのを避けながら、なるべく公平に取得をすすめます。「勝手に休暇を入れられた!」という不満を招かないよう、事前の準備が必要です。
※「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、雇用主側が労働者に、あらかじめ特定の期間を指定して年次有給休暇を付与する(取得させる)仕組みです。導入について労使協定を締結します。年間最低5日は労働者の自由に利用できる日数とします。
・半日単位・時間単位の年次有給休暇利用を導入しましょう
現在の労働基準法では、休暇の取得単位は1日または半日。しかし2010年4月からは、法改正により労使協定を結べば時間単位での取得もできるようになります(年間5日まで)。育児や介護、ちょっとした用事のために時間単位の休暇を歓迎するスタッフは多いはず。利用のルールづくりを始めましょう。
・未消化年休は「貯蓄制度」で活用を
年度替りで未消化の年休が消えてしまう!こんなケースにお勧めしたいのが、時効で消滅する年次有給休暇を積み立てて、いざというとき活用する仕組みです。使用目的は(1)病気休養(2)看護・介護(3)リフレッシュ(4)ボランティア(5)自己啓発(6)災害(7)再就職準備など。すでに多くの企業で導入されています。
・注意! 有給休暇取得の取得制限は違法行為になる場合もあります
「有給休暇が取得できない」との相談が日本看護協会へ多数寄せられています。「上司が部下に取得してはならないと伝える」「取得日数の限度を示す」「取得理由を限定する」などの行為は労働基準法違反の疑いがあります。
有給休暇は職員の希望期日に取得させることが原則です。ただし、その日に休暇が集中するため「事業の正常な運営を妨げる場合」に、使用者は労働者から指定のあった年次有給休暇を別の日にするよう変更を命じることができます(時季変更権)。中には7対1の算定要件の維持を理由として、有給休暇取得を制限する例がありますが、有給休暇の消化をはじめ、産休、育休、病欠、研修、会議等の時間を見込んだ人員配置が必要です。
日本看護協会としては法令順守できる人員配置が担保されるよう診療報酬の改定を求めていきます。
有給が取れない場合
公益社団法人日本看護協会の労働に関するよくあるご質問より、有給が取れない場合に関する質問を紹介します。
質問:私の職場では入院基本料の基準が上がりましたが、それ以後、「人が足りないから」と有給休暇を取らせてもらえません。法的に問題はないのでしょうか
回答:有給休暇取得は労働基準法に定められた権利であり、一般に取得制限は違法行為です。「上司が部下に取得してはならないと伝える」「取得日数の限度を示す」「取得理由を限定する」などの行為は、労働基準法違反となります。
有給休暇は、職員の希望期日に取得させることが原則です。雇い主は「事業の正常な運営を妨げるおそれがある」場合に限って取得期日を変更する権利(時季変更権)がありますが、常時人員不足で「入院基本料の算定要件の維持が困難である」場合は該当しません。
法律を守れる、ゆとりある職員配置が必要です。なお、職員の有給休暇取得を平準化して恒常的に一定のレベルの看護体制を維持するために、労使協定による有給休暇の計画的付与制度を導入することができます。
有給を取る理由について
公益社団法人日本看護協会の労働に関するよくあるご質問より、有給を取る理由に関する質問を紹介します。
質問:有給休暇を取る理由を具体的に定めていますが、問題はないでしょうか
回答:労働者の請求する時季に有給休暇を付与することが使用者の義務として定められているため、理由を問いその取得を制限することは違法となります。また、労働者は、使用者から有給休暇の使用目的を尋ねられてもこれを明らかにする義務はないとされています。
使用者には、労働者が有給休暇を取得しやすい環境の整備が義務付けられています。具体的には、個人別年次有給休暇取得計画表の作成、取得状況の把握、業務体制の整備・業務量の正確な把握、半日有給休暇取得促進、2週間程度の連続した長期休暇の取得促進等が推奨されています(「労働時間等見直しガイドライン」<労働時間等設定改善指針>平成20年厚生労働省告示第108号)。なお、労働基準法改正により、2010(平成22)年4月から労使協定により年間5日まで、時間単位での取得が認められるようになりました。
パートの有給について
公益社団法人日本看護協会の労働に関するよくあるご質問より、パートの有給に関する質問を紹介します。
質問:「パートなので有給休暇はない」と言われました。
回答:パートタイム労働者にも労働基準法の規定に基づき有給休暇の付与が義務付けられています。日数は週所定労働時間や年間・週所定労働日数、勤続期間などによって異なるため、個々のパートタイム労働者の勤務状況に見合った有給休暇日数の算出が必要です。
労働基準法では、使用者は雇い入れの日から起算して6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10日の有給休暇を与えるよう定めています。
有給休暇は、賃金が保証され、労働義務が免除される労働日であり、企業規模や従業員の業務成績、正社員、派遣社員、パートかといった雇用形態に関わりなく、在籍年数や労働時間に比例して付与されます。
看護師の休暇申請のコツ
続いては、看護師の休暇申請のコツを紹介します。
病院は常に患者さんで溢れており、看護師のニーズも高いという特徴があります。
そんな職場で希望通りに休むためにはいくつかのコツがあります。
今回は休暇をスムーズに取得するコツを4つ厳選しました。
早めに休暇希望を出す
看護師の休暇申請のコツ1つ目は、早めに休暇希望を出すことです。
早めに休暇を申請することで、管理者もシフトを制作しやすくなります。
直前に休み希望を出すと、なかなか希望通りに休めないケースも。
まとまった休暇を希望する場合には、事前に看護師長や看護主任に相談しておくとスムーズです。
同僚とコミュニケーションを取る
看護師の休暇申請のコツ2つ目は、同僚とコミュニケーションを取ることです。
同僚と休暇申請の時期が被ってしまうと、希望日に休みが取れない可能性があります。
同僚とはこまめにコミュニケーションを取り、いつ頃休みを取る予定なのか聞いておきましょう。
特に長期休みを希望する際には、事前に休み希望がかぶらないように調整する必要があります。
また、こまめに会話をしておくことで同僚間の仲が深まり、シフト交換もスムーズになるという利点もあります。
月をまたいで休暇を取る
看護師の休暇申請のコツ3つ目は、月をまたいで休暇を取ることです。
月末と月初に休みを申請することで、連休が取りやすくなります。
ただし、毎月毎月月をまたいで休暇を取っていると、同僚や先輩から目をつけられてしまうかもしれません。
連休が欲しい場合や予定がある場合にだけ、月をまたいで休暇を取得しましょう。
休みが取りやすい職場に転職する
看護師の休暇申請のコツ4つ目は、休みが取りやすい職場に転職することです。
どうしても休暇申請が希望通りにいかない場合には、転職を検討することも一つの手です。
大学病院や国立病院などの大規模な職場では、休暇体制も整っており、休みが取りやすいケースもあります。
また、介護施設やクリニックなどの日勤のみのスケジュールの職場も、比較的休みが取りやすいでしょう。
看護師の長期休みの過ごし方
最後に、看護師の長期休みの過ごし方を紹介します。
長期休みを有効活用し、気分をリフレッシュしましょう。
旅行
看護師の長期休みの過ごし方1つ目は、旅行です。
長期休みを利用して海外に旅行するのもおすすめです。
非日常的な体験で、気分もしっかりとリフレッシュできるでしょう。
休み明けの英気を養える休暇の過ごし方です。
勉強する
看護師の長期休みの過ごし方2つ目は、勉強することです。
仕事終わりは疲れていてなかなか勉強できていない、という方におすすめの休暇の過ごし方です。
一年に一度の長期休暇で、その年学んだことをしっかりと復習することで、知識を身につけることができます。
看護師として専門資格の取得やキャリアアップを目指している方は、自己研鑽のために時間を使うのも良いでしょう。
まとめ
今回は看護師の長期休みに関する情報をまとめました。
しっかりと働くことは大切なことですが、同じくらい休むことも大切です。
激務の職場では、なかなかまとまった休みを取るのが難しいこともありますが、定期的に体を休めないと病気や怪我につながってしまうこともあります。
休暇を申請する際は、早めに申請したり同僚とコミュニケーションを取ることでスムーズに進めることができます。
ぜひ、この記事を参考にして長期休暇を満喫しましょう。