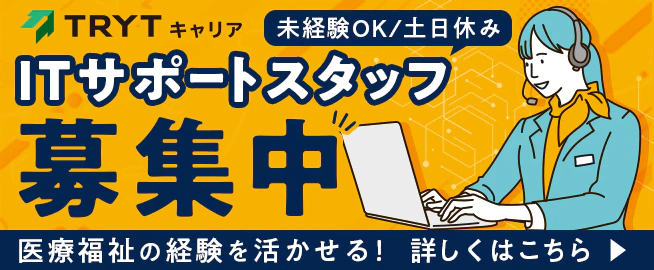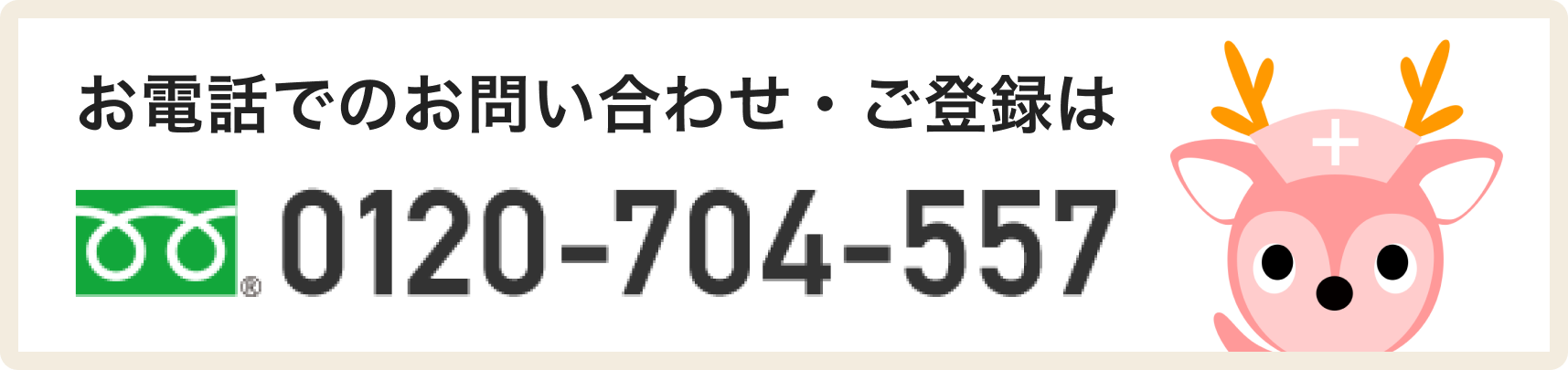子育てをしている看護師必見!育児と仕事を両立させる方法とは?

出産や子育てなどのライフイベントは、人生の中で大きな転換期となります。
子育てを機に職場を離れる方もいますが、キャリアを築くためには、両立する方法を検討する必要があります。
今回は子育てをしている看護師さんや、出産を控えている看護師さんに向けて、育児と仕事を両立させる方法を解説します。
ぜひ参考にご覧ください。
子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法
さっそくですが、子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法について紹介します。
院内託児所を利用する、保育所・学童保育を利用する、家族に協力してもらう、派遣看護師として働くという4つの方法について見ていきましょう。
院内託児所を利用する
子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法1つ目は、院内託児所を利用することです。
院内託児所とは、施設で働く医師や看護師が子どもを預けられる保育施設です。
昼夜問わず働く医療従事者のために、夜間まで利用できる託児所もあります。
中には、24時間365日開園しているケースも。
また、託児所の中には学童保育や病児保育の機能を持ち合わせている施設もあります。
医療従事者のニーズに応える施設ですので、育児と仕事の両立を支えてくれるでしょう。
保育所・学童保育を利用する
子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法2つ目は、保育所・学童保育を利用することです。
保育所は、厚生労働省が管轄している施設です。
保護者に代わって子どもを預かってくれるので、安心して仕事に出向くことができます。
保育所では、療育や教育を目的としており、おむつ着替えや更衣、食事の介助を通して、子どもの健やかな成長を育んでくれます。
基本的に、0歳〜小学校入学前までの子どもが利用可能です。
一方、学童保育とは主に放課後や長期休暇中に子どもを預かってくれる施設で、遊びや勉強の場として機能しています。
厚生労働省や文部科学省、民間法人などが管轄しています。
小学1年生〜6年生までの留守家庭の小学生が利用できます。
子供を保育所や学童保育に預けることで、仕事もスムーズにこなせるでしょう。
家族に協力してもらう
子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法3つ目は、家族に協力してもらうことです。
家族の協力を得ることで、仕事に出かけることができます。
父親が子どもの面倒を見たり、母や義母、祖父母などに協力を仰ぐケースもあります。
家族で一丸となって子育てに取り組むことは、子どもの発育にも良い影響を与えます。
現在母親だけで子育てを行っている家庭は、看護師として働くうえでの負担を考慮し、家族とよく相談し合うことが大切です。
派遣看護師として働く
子育て中の看護師が育児と仕事を両立させる方法4つ目は、派遣看護師として働くことです。
正規の社員ではなく、派遣社員として医療現場に出向くことで、柔軟な働き方ができます。
就業時間の融通も利くので、子育てとの両立もしやすいでしょう。
派遣看護師としての働き先には、病院やクリニック、介護老人保健施設など、さまざまな場所があります。
子育て中の看護師におすすめな職場
続いては、子育て中の看護師におすすめな職場を紹介します。
子育てをしながら働く看護師にとって、勤務時間や休日の確保はとても重要です。
柔軟な働き方が可能な施設は、仕事と子育ての両立もしやすいでしょう。
子育て中の看護師におすすめな職場には、クリニック、訪問介護、デイケア・デイサービス、健診(検診)センター、保育園などがあります。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
クリニック
子育て中の看護師におすすめな職場1つ目は、クリニックです。
病床を持たないクリニックであれば、夜勤がありません。
日勤のみで働くことができるので、子育てとも両立しやすい傾向にあります。
外来診療のみなら、比較的残業も少なく、定時に帰れる日も多いでしょう。
また、土日祝日はクリニック自体が休みのケースも多いため、お子さんの学校と休みを合わせられるのも嬉しいポイントです。
訪問介護
子育て中の看護師におすすめな職場2つ目は、訪問介護です。
訪問看護ステーションで働くことで、夜勤をせずに日勤のみで働けます。
土日が休みとなる可能性も高いので、お子さんの学校と休みを合わせることができます。
ただし、オンコール対応のある訪問看護ステーションも存在しますので、多少忙しさを感じることがあるかもしれません。
オンコール対応の有無は施設によって異なりますので、事前に頻度などを確認しておきましょう。
デイケア・デイサービス
子育て中の看護師におすすめな職場3つ目は、デイケア・デイサービスです。
デイケア・デイサービスなどの介護施設は、基本的に夜勤がありません。
日勤のみなので、スケジュールを調整すればお子さんが帰って来る頃に帰宅することも可能です。
また、土日が休みのケースも多いので、お子さんの学校と休みを合わせることができます。
同じ境遇のママさんやパパさんが働いているケースも多いので、心理的な安心感もメリットだと言えるでしょう。
健診(検診)センター
子育て中の看護師におすすめな職場4つ目は、健診(検診)センターです。
健診(検診)センターは、病気の早期発見や生活習慣の見直しを推進する施設です。
採血を中心に、患者さんのケアを行いますが、基本的に健康な方が訪れます。
健診(検診)センターも、これまで紹介した施設同様に夜勤がありません。
残業も少ないので、ライフワークバランスを保てるでしょう。
プライベート重視な方にとってもおすすめの職場です。
保育園
子育て中の看護師におすすめな職場5つ目は、保育園です。
看護師は、保育園などの保育施設で働くことも可能です。
園児の健康管理や健診の補助、保育士のサポートを行います。
園の行事以外では日曜祝日は休みのため、子育てと仕事が両立しやすいでしょう。
子育ての経験も活かせる職場なので、ママさん・パパさんのやりがいも大きいかもしれません。
子育て中の看護師が知っておきたい勤務先の制度
続いては、子育て中の看護師が知っておきたい勤務先の制度について解説します。
時間外労働の制限、育児短時間勤務制度、短時間正社員制度について見ていきましょう。
時間外労働の制限
育児・介護休業法には、法定時間外労働の制限が定められています。
これは、お子さんが小学校就学前までの方が利用できる制度です。
制度の概要、対象となる従業員、手続きは以下の通りです。
「制度の概要
小学校就学前までの子を養育する従業員は、事業主に申し出ることにより、小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや、子に予防接種または健康診断を受けさせるために利用することができます。
対象となる従業員
原則として、小学校就学前までの子を養育する全ての男女労働者(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には、対象となりません。
手続
子の看護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し出る必要があります。子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を認め、書面の提出等を求める場合は、事後となっても差し支えないこととすることが必要です。」
育児短時間勤務制度
育児・介護休業法には、短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)が定められています。
これは、お子さんが3歳未満の方が利用できる制度です。
制度の概要、対象となる従業員、手続きは以下の通りです。
「制度の概要
事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
対象となる従業員
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女労働者です。
①3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていない
こと。
②日々雇用される従業員でないこと。
③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
④労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)~ウ)の従業員は、労使協定により適用除外とする場合があります。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認
められる業務に従事する従業員
※このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以
下のいずれかの制度を講じなければなりません。
(a)育児休業に関する制度に準ずる措置
(b)フレックスタイム制度
(c)始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
(d)従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
手続
短時間勤務制度の適用を受けるための手続は、就業規則等の定めによります。こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。」
短時間正社員制度
育児・介護休業法には、短時間正社員制度が定められています。
これは、お子さんが3歳未満の方が利用できる制度です。
制度の概要、対象となる従業員、手続きは以下の通りです。
「制度の概要
事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。短時間勤務制度は、1日の所定労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
対象となる従業員
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女労働者です。
①3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
②日々雇用される従業員でないこと。
③1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
④労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)~ウ)の従業員は、労使協定により適用除外とする場合があります。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
※このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません。
(a)育児休業に関する制度に準ずる措置
(b)フレックスタイム制度
(c)始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
(d)従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
手続
短時間勤務制度の適用を受けるための手続は、就業規則等の定めによります。こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。」
子育てをしながら看護師として働くためには
最後に、子育てをしながら看護師として働くためのポイントを解説します。
家事や育児の悩みを家族で共有する
子育てをしながら看護師として働くためには、家事や育児の悩みを家族で共有することが大切です。
家事や育児の悩みを一人で抱え込むことは、精神衛生上悪い影響を及ぼします。
人に話すこと、相談することで解決する悩みもありますので、まずは家族に思っていることを伝えてみましょう。
悩み事は上司に相談する
子育てをしながら看護師として働くためには、悩み事を上司に相談することが大切です。
働くうえでの悩みや疑問点、問題点は職場の上司に相談してみましょう。
上司と話し合うことで、解決できる問題があるかもしれません。
まとめ
今回は、子育てをしている看護師さんに向けて、育児と仕事を両立させる方法を紹介しました。
ワークライフバランスを整えるために利用できる施設や制度はさまざまです。
育児と仕事の両立で不安を感じないためにも、家族や上司とよく相談し、働きやすい環境作りを行いましょう。