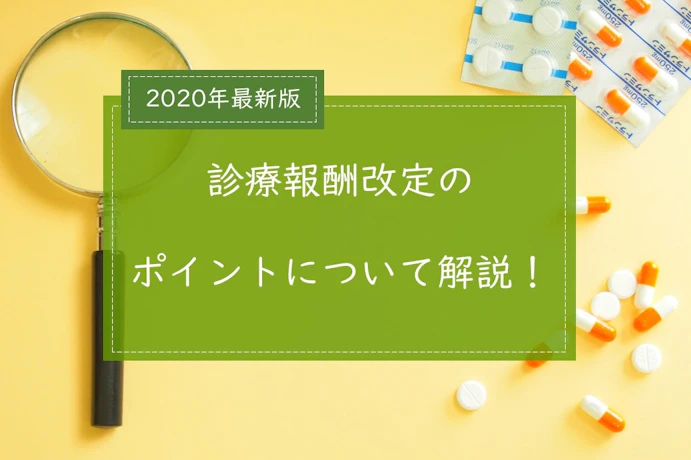お役立ち情報
公開日:2023.10.18
更新日:2023.10.31
【令和2年/2020年度版】看護師向け診療報酬改定のポイントについて解説!
#診療報酬
目次
令和2年(2020年)に行われた、診療報酬の改定は“医師の働き方改革”が大きなテーマとなっています。その多くは勤務医のためのものですが、看護師に関わる内容もいくつか見直されるようになりました。具体的にどのように見直しが行われたのでしょうか。
診療報酬の基本情報と看護師をメインとした改定ポイントについてご紹介していきます。
診療報酬の基本情報と看護師をメインとした改定ポイントについてご紹介していきます。
診療報酬とは
診療報酬とは、患者さんが病気や怪我などにより医師などから受ける医療行為に対して、保険証を提示し保険制度から支払われる料金のことをいいます。診療報酬の項目としては、患者さんが初めて来院したときの初診料や再診料、入院料、検査料、画像診断など、およそ14,000項目以上あるとされています。
よく「診療報酬はそのまま医師の給料になっちゃうの…?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますがそうではありません。医師や看護師の人件費となるだけではなく、病院やクリニックなど施設の維持費や管理費のほか、薬品や医療材料の購入費にも診療報酬は充てられているのです。
よく「診療報酬はそのまま医師の給料になっちゃうの…?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますがそうではありません。医師や看護師の人件費となるだけではなく、病院やクリニックなど施設の維持費や管理費のほか、薬品や医療材料の購入費にも診療報酬は充てられているのです。
診療報酬はどんな料金?
次に、診療報酬がどのような仕組みとなっているのか具体的に解説していきます。
診療報酬は全額を患者が負担するのではなく、
この国民皆保険制度を利用することで、国民は安価で治療を受けることができるのです。
この診療報酬についてですが冒頭でもお話したように「診療報酬=医師(看護師)の収入」ではありません。施設の維持費や管理費、薬品や材料費としても割り振られています。そのため、万が一診療報酬改定により加点となっていたものが減点となった場合、病院の経営自体に大きく影響してしまう恐れがあるのです。
通常、2年に1回行われる診療報酬改定ですが、協議内容を把握することで国がどこに力を入れているのか(需要が増えているのか)、それによって今後診療報酬がどう変化していくのかを推測することができます。
では、その診療報酬は誰が決めているのでしょうか?
診療報酬の決め方と全体のスケジュールについて解説していきます。
診療報酬は全額を患者が負担するのではなく、
患者が3割、残りの7割を保険者が負担しています
。保険者とは、健康保険事業の運営主体のことを指します。原則、国民は国民皆保険制度に則り国民健康保険または健康保険組合など、職業に応じた公的保険に加入する必要があります。この国民皆保険制度を利用することで、国民は安価で治療を受けることができるのです。
この診療報酬についてですが冒頭でもお話したように「診療報酬=医師(看護師)の収入」ではありません。施設の維持費や管理費、薬品や材料費としても割り振られています。そのため、万が一診療報酬改定により加点となっていたものが減点となった場合、病院の経営自体に大きく影響してしまう恐れがあるのです。
通常、2年に1回行われる診療報酬改定ですが、協議内容を把握することで国がどこに力を入れているのか(需要が増えているのか)、それによって今後診療報酬がどう変化していくのかを推測することができます。
では、その診療報酬は誰が決めているのでしょうか?
診療報酬の決め方と全体のスケジュールについて解説していきます。
診療報酬の決め方は?
診療報酬は、経済状況や医療の状況に応じて厚生労働大臣、社会保障審議会(厚労省)、内閣府、中央社会保険医療協議会(以降、中医協と省略する)の4つの機関によって2年に一度の間隔で診療報酬の改定内容が決められます。
ここで、先に中協医とはなにかについて説明します。
中央社会保険医療協議会とは、診療報酬の改定や薬価、保険材料価格の改定などの案件を厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、文書をもって答申する協議会のことをいいます。簡単に説明すると、「公益委員(有識者)」「診療側委員(医療機関)」「支払側委員(保険組合など)」の3つで構成されており、それぞれの観点から意見を出し合い協議を重ねます。
次に、どのような流れで新たな診療報酬を決めるのか解説していきます。
おもな流れとしては、最初に社会保障審議会(厚生労働省)が診療報酬改定の基本方針を決定します。そして内閣府が、診療報酬の改定率を決定したのち、厚生労働大臣に提出。厚生労働大臣は中医協に改定案の諮問を依頼し、新たな改定内容について中協医は議論を重ねます。話し合いの末に決定された改定案は厚生労働大臣に提出し、認められたものが『新たな診療報酬』となるのです。
ここで、先に中協医とはなにかについて説明します。
中央社会保険医療協議会とは、診療報酬の改定や薬価、保険材料価格の改定などの案件を厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、文書をもって答申する協議会のことをいいます。簡単に説明すると、「公益委員(有識者)」「診療側委員(医療機関)」「支払側委員(保険組合など)」の3つで構成されており、それぞれの観点から意見を出し合い協議を重ねます。
次に、どのような流れで新たな診療報酬を決めるのか解説していきます。
おもな流れとしては、最初に社会保障審議会(厚生労働省)が診療報酬改定の基本方針を決定します。そして内閣府が、診療報酬の改定率を決定したのち、厚生労働大臣に提出。厚生労働大臣は中医協に改定案の諮問を依頼し、新たな改定内容について中協医は議論を重ねます。話し合いの末に決定された改定案は厚生労働大臣に提出し、認められたものが『新たな診療報酬』となるのです。
診療報酬改定のスケジュール
この診療報酬改定ですが、具体的にどのようなスケジュールで確定されるのでしょうか。厚生労働省が公表している令和2年の診療報酬改定スケジュール(案)をもとに大まかな流れをみていきましょう。
令和元年の秋~12月頃にかけて、社会保障審議会(略:社保審)は診療報酬改定の基本方針を決定します。その後、内閣により診療報酬の改定率が決定され、翌年の2月上旬頃には中協医の議論のもと改定案が提出されます。厚生労働大臣の告示や通知が行われるのが3月上旬頃。翌月の4月1日に新たな診療報酬が施行されました。
診療報酬が改定される際に、注目するべきポイントは『社保審の基本方針の策定内容』と『1月~12月頃の中協医の審議内容』です。これらの内容をおさえることで、今後国はどこに力を入れていきたいのか、診療報酬が変わるであろう項目を大まかに知ることができます。また、年内に行われる中医協の審議内容をチェックすることで支払い側と診療側の提言を比較し今後どのような診療報酬となるのか推測することができます。
令和2年/2020年度の診療報酬改定の内容
それでは、実際に令和2年に改定された診療報酬のおもな内容をみていきましょう。どのような項目が追加されたのか、改定されたことで看護師にどのようなメリットがあるのかを解説していきます。
改定率について
令和2年の改定に伴う診療報酬の改定率ですが、以下のような内訳となります。
【令和2年 診療報酬改定に伴う改定率】
薬価 -0.99%(▽1100億円)
材料価格 -0.02%(▽30億円)
全体 -0.46%(▽500億円)
本体となる改定率は+0.55%、金額にして約600億円程度。この本体というのは、医師や歯科医、薬剤師などの収入に大きく関係するものとなり、割合が大きくなるということはそれだけ
本体の+0.55%の内、+0.08%分(公費126億円、国費95.3億円)は勤務医の働き方改革への特例措置として位置づけられます。また働き方改革への対応では、地域医療総合確保基金でも公費143億円を積み増し、今後診療報酬と両方で対応すると厚労省は説明しています。
【令和2年 診療報酬改定に伴う改定率】
本体 +0.55%(▲600億円)
薬価 -0.99%(▽1100億円)
材料価格 -0.02%(▽30億円)
全体 -0.46%(▽500億円)
本体となる改定率は+0.55%、金額にして約600億円程度。この本体というのは、医師や歯科医、薬剤師などの収入に大きく関係するものとなり、割合が大きくなるということはそれだけ
「医療従事者の収入が増える」
ということです。厳しい財政事情の中、医療機関の経営状況や、賃金・物価の動向を踏まえ2018年度改定と同じ0.55%となりました。本体の+0.55%の内、+0.08%分(公費126億円、国費95.3億円)は勤務医の働き方改革への特例措置として位置づけられます。また働き方改革への対応では、地域医療総合確保基金でも公費143億円を積み増し、今後診療報酬と両方で対応すると厚労省は説明しています。
改定における基本方針とおもな項目について
2020年度診療報酬改定における基本方針とおもな項目については以下の4つとなっています。
Ⅰ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進
2024年4月から、医者の時間外労働の上限が決められるようになります。そこで各医療機関は労働時間の短縮に伴い、それぞれの病院で対策を進めていく必要があります。
事務作業を医者以外のスタッフが行うなど、すでに診療報酬でも評価しているものもありますよね。労働時間が減っても、患者さんへの治療の質が落ちることのないように、スタッフ全体で仕事の分担をしていくことが求められます。
このような施策は、今後診療報酬のなかで評価できるよう検討されることとなるでしょう。
Ⅱ 患者・国民にとって身近であり、安心・安全で質の高い医療の実現
この取り組みは、患者さんにとって安心で安全であることが大前提となります。新しい治療法や医療機器などが出てくることにより、結核などの感染症は減少してきました。
このように医療の環境が日々変化していることを考慮しながら第3者の視点で評価する必要があるのです。第3者の評価とは、病院外の組織が病院のことをみて良い点・悪い点を判断しスコアをつけていくというもの。かかりつけ医(歯科医、薬局などを含む)医療機関の機能はどうか、日本の医療の中で、特に対応が必要な分野について評価を行うことで、国民にとって安心安全で質の高い医療を提供する取り組みのことをいいます。
Ⅲ 医療機関の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進
急性期・回復期・慢性期など、患者さんの状態に応じた治療が切れ目なく行われなければなりません。そのためには、病院同士の連携や在宅医療・訪問看護、介護サービスなどの準備が必要となります。例えば、入院してきた患者さんの状態に応じて、手術が必要か、どんな薬を処方するか、看護のケア、今後のリハビリの内容など、その場その場で必要な医療を提供します。また本来、大学病院や大病院に係る際は紹介状が無いと5,000円以上の特別料金を支払わなければなりません。そこで、大病院で治療や検査を行う際には“診療所やクリニックで紹介状を書いてもらい大病院でより精密な治療・検査を行う”この流れをきちんと構築していく必要があるのです。
Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上
年々、国民の平均寿命は伸びてきています。最新医療機器の導入や医療に関する技術が高くなり、同時に素晴らしい薬が次々と開発されてきたことが理由として挙げられます。しかし、高いレベルの医療を求めるということは、それだけ医療に係る費用が増えるということ…。そこで国民皆保険制度を維持するために、医療関係者のサービスの向上と費用対効果制度を利用した薬価の適正化、病院と薬局が連携して患者さんに医薬品の適正使用を促すことが重要視されています。
これら4つの項目のなかで、看護師さんにとって重要となってくるのが「医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進」です。では、具体的にどのような内容となっているのでしょうか。次に、働き方改革の推進について詳しく解説していきます。
看護師は要チェック!『働き方改革の推進について』
今回、改定された診療報酬のなかで最も重要とされているのが『医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進』です。おもに医師の長時間勤務を筆頭とする救急病院または急性期病院などの労働環境を改善するための取り組みといえます。
例えば、
などといったことが具体的に挙げられます。
また、看護師にとってもいくつか改善されるポイントがあるので簡単にご紹介します。
例えば、
・タイムカードを使って正しく労務管理を行う。労働環境が良くなるように取り組む
・医師にすべて任せるのではなく、看護師や事務スタッフと業務を分担する
・届出や報告は簡素化する
・人の配置をもっと効率の良いものにする
・すぐに治療が必要な患者さんに救急医療を提供する
・業務効率化のためにICTを活用する
などといったことが具体的に挙げられます。
また、看護師にとってもいくつか改善されるポイントがあるので簡単にご紹介します。
看護補助者の配置で報酬がアップされる!
今回の診療報酬改定内容のなかで、看護補助の配置に関して以前より点数が加算される見直しがありました。おもに看護職員の負担を軽減するとともに、看護補助者との業務分担・協働を推進することを目的としています。
まずは、どのような基準で点数が加算されるのか以下の表を見てみましょう。
まずは、どのような基準で点数が加算されるのか以下の表を見てみましょう。
このように『急性期看護補助体制加算』と『看護補助加算』の二つが改定されることとなりました。『急性期看護補助体制加算』とは、急性期病院で看護補助者に係るものとなります。
例えば、25対1(看護補助者5割以上)の項目ですと、以前は210点だったところを240点まで引き上げとなります。この『25対1(看護補助者5割以上)』は看護配置のことです。患者さん25人に対して看護補助者を1人配置しなければなりません。つまり100床の病院であれば、看護補助者を4人配置する必要があるのです。看護要員のうち看護補助者が5割以上またはそれ以下によって加算される点数は異なります。
注意しなければならないのが、体制加算には『1日につき14日まで』といった期間が設けられています。患者さんが入院してから最大2週間以内に退院した場合、これらの加算が適用されます。2週間を超える長期入院には加算されませんので注意しましょう。
また今回、急性期看護補助体制加算に加えて“ある条件を満たす”ことで『夜間看護体制加算』を加算することができます。『夜間看護体制加算』についても一部改定が行われたので次の項目でチェックしてみましょう。
例えば、25対1(看護補助者5割以上)の項目ですと、以前は210点だったところを240点まで引き上げとなります。この『25対1(看護補助者5割以上)』は看護配置のことです。患者さん25人に対して看護補助者を1人配置しなければなりません。つまり100床の病院であれば、看護補助者を4人配置する必要があるのです。看護要員のうち看護補助者が5割以上またはそれ以下によって加算される点数は異なります。
注意しなければならないのが、体制加算には『1日につき14日まで』といった期間が設けられています。患者さんが入院してから最大2週間以内に退院した場合、これらの加算が適用されます。2週間を超える長期入院には加算されませんので注意しましょう。
また今回、急性期看護補助体制加算に加えて“ある条件を満たす”ことで『夜間看護体制加算』を加算することができます。『夜間看護体制加算』についても一部改定が行われたので次の項目でチェックしてみましょう。
「夜間看護体制」の見直しで看護体制が充実
夜間看護体制に関して、新たな項目と見直しがされることとなりました。
【夜間看護体制を満たす必要のある項目】
●勤務間インターバルを11時間確保している
●3交代制、勤務開始時間は24時間を空ける
●連続夜勤は2回まで
●夜勤明けの暦日は休日を確保している NEW
●早出・遅出を柔軟に組み込む NEW
●業務量を把握・管理するシステムを導入している
●看護補助業務のうち5割以上が療養生活上の世話
●看護補助者が5割以上である
●院内保育所がある 見直し
●ICT、AI、IoTを使っている NEW
●夜間急性期看護補助体制加算を届けている(※)
※看護職員夜間配置加算を受けるうえでの条件
●勤務間インターバルを11時間確保している
●3交代制、勤務開始時間は24時間を空ける
●連続夜勤は2回まで
●夜勤明けの暦日は休日を確保している NEW
●早出・遅出を柔軟に組み込む NEW
●業務量を把握・管理するシステムを導入している
●看護補助業務のうち5割以上が療養生活上の世話
●看護補助者が5割以上である
●院内保育所がある 見直し
●ICT、AI、IoTを使っている NEW
●夜間急性期看護補助体制加算を届けている(※)
※看護職員夜間配置加算を受けるうえでの条件
これらの条件のなかで特に注目すべき点は『夜勤後の休日』が加算の条件に加わったことです。従来から「勤務間のインターバルを11時間確保する」「連続夜勤は2回まで」といった勤務体制に関する条件があるなかで、より夜勤看護師の配置を手厚くするために
“夜勤明けの暦日は休日を確保する”
といった項目が新たに増えました。暦日の休日とは、午前0時から午後12時までの24時間を休みにするということ。交代勤務で負担の大きい看護師の労働環境を改善することを目的としています。
「特定行為看護師」が注目されている
今回の改定により、“特定行為研修を修了した看護師”に対して診療報酬上の評価が増えることとなりました。
おもに急性期病院を対象とした加算のなかで、総合入院体制加算というものがあります。この加算に
2024年4月から本格化する「医師の働き方改革」では原則、時間外労働上限が960時間以内に設定されます。そのため、医師から他職種へのタスク・シフティングを積極的に進めていく必要があり、例年以上に特定看護師の需要は高くなることが予想されます。
おもに急性期病院を対象とした加算のなかで、総合入院体制加算というものがあります。この加算に
“特定行為研修を修了した看護師が複数いて、勤務医の負担を軽減すること”
が条件に加えられたのです。2024年4月から本格化する「医師の働き方改革」では原則、時間外労働上限が960時間以内に設定されます。そのため、医師から他職種へのタスク・シフティングを積極的に進めていく必要があり、例年以上に特定看護師の需要は高くなることが予想されます。
新たに『地域医療体制』の確保がされる
働き方改革の推進により、看護補助者による看護師の業務負担が軽減される一方で、救急医療を行う医療機関の業務分担も新たな加算により軽減できるのではないかとされています。
そのひとつが「地域医療体制確保加算」です。
「地域医療体制確保加算」とは、救急医療を提供している病院を対象に医師の負担を軽減させるとともに
そのひとつが「地域医療体制確保加算」です。
「地域医療体制確保加算」とは、救急医療を提供している病院を対象に医師の負担を軽減させるとともに
救急搬送受け入れた分だけ入院初日の入院料を+520点加算する
というものです。この体制加算に関しては、以下の施設基準を満たす必要があります。【施設基準】
●救急用の自動車または救急医療用のヘリコプターによる搬送件数が年間で2,000件以上であること
●以下、6か条を守っていること
1、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性などについて提言するための責任者を配置すること
2、当直や夜間の勤務状況を把握していること
3、病院内に、多職種のチーム委員会か会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減および処遇の改善に資する計画」を作成していること
4、計画はしっかり目標を立てて、問題点を把握して定期的に見直すこと
5、「病院勤務医の負担の軽減および処遇の改善に資する計画」は次の項目を記載すること
・具体的な役割分担を明確に取り決めること
・勤務の計画上、連続当直にならないようなシフト体制
・勤務間のインターバル
・オペの予定がある医師は、夜勤や当直を避けてあげる配慮
・当直明けの先生の仕事内容には配慮
・交代勤務制・複数主治医の実施
・育児や介護に関する法律のルールに沿った、短時間正規雇用ドクターの採用
6、これらの取り組みを院内に掲示すること
●救急用の自動車または救急医療用のヘリコプターによる搬送件数が年間で2,000件以上であること
●以下、6か条を守っていること
1、病院勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性などについて提言するための責任者を配置すること
2、当直や夜間の勤務状況を把握していること
3、病院内に、多職種のチーム委員会か会議を設置し、「病院勤務医の負担の軽減および処遇の改善に資する計画」を作成していること
4、計画はしっかり目標を立てて、問題点を把握して定期的に見直すこと
5、「病院勤務医の負担の軽減および処遇の改善に資する計画」は次の項目を記載すること
・具体的な役割分担を明確に取り決めること
・勤務の計画上、連続当直にならないようなシフト体制
・勤務間のインターバル
・オペの予定がある医師は、夜勤や当直を避けてあげる配慮
・当直明けの先生の仕事内容には配慮
・交代勤務制・複数主治医の実施
・育児や介護に関する法律のルールに沿った、短時間正規雇用ドクターの採用
6、これらの取り組みを院内に掲示すること
この体制加算を受ける際に、注意しなければならないのが「救急搬送を年間2000件以上受け入れている病院」という点です。年間2,000件(1日あたり5件程度)受け入れるということは、おそらく400床以上の大きな病院が対象となることでしょう。
520点と点数も高いことから、今後積極的に取り入れる病院が増えてくる可能性があります。
また、それとは別に「救急搬送看護体制加算1」というものがあります。
これは、救急搬送を年間1,000件以上受け入れている病院であること、専任の看護師を複数名配置していることを条件に400点加算されます。今後、これらの加算が対象となる病院では、救急部門の看護師の配置が増えるかもしれません。
さいごに
今回の診療報酬改定において、膨大な改定内容のなかでも「医師の働き方改革」が最初の項目として取り上げられていることから分かるように、国としても『医師(看護師)の負担をいかに減らせられるか』という点は最重要課題とされています。
診療報酬の改定内容によっては看護師としての働き方や、施設の運営基準にも影響を及ぼす恐れがあります。看護師として求められる人材も変わってくるため、自分のキャリアなどについて相談したい方はぜひ看護師ワーカーをご利用してみてはいかがでしょうか。
◆看護師ワーカーに相談してみる(無料)
診療報酬の改定内容によっては看護師としての働き方や、施設の運営基準にも影響を及ぼす恐れがあります。看護師として求められる人材も変わってくるため、自分のキャリアなどについて相談したい方はぜひ看護師ワーカーをご利用してみてはいかがでしょうか。
◆看護師ワーカーに相談してみる(無料)
#診療報酬
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.