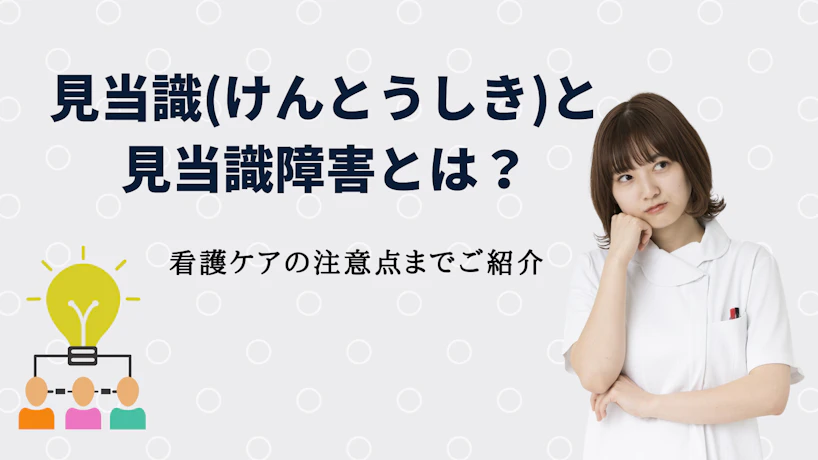看護知識
公開日:2023.10.18
更新日:2023.10.24
見当識(けんとうしき)と見当識障害とは?看護ケアの注意点までご紹介
目次
「見当識」とは?医療や介護の現場ではよく耳にする言葉「見当識」ですが、普段高齢者と関わりのない人にとってはあまり聞きなれない言葉でしょう。今回は、見当識と見当識障害について詳しく解説していきます。見当識を保つリハビリについてもご紹介するので、最後までご覧くださいね。
見当識(けんとうしき)と見当識障害の意味とは?
見当識とは記憶や視覚の認知機能に関係しているもので、日付や時刻・場所や周りの状況・人の把握をしながら、自分の置かれている状況を理解する能力のことです。
見当識障害とは、見当識の能力が失われ通常の日常生活が送れなくなってしまった状態のことで、アルツハイマー型認知症の中核症状のひとつです。
見当識障害とは、見当識の能力が失われ通常の日常生活が送れなくなってしまった状態のことで、アルツハイマー型認知症の中核症状のひとつです。
見当識障害(失見当識)の種類
見当識障害は失見当識(しつけんとうしき)とも呼ばれます。表れ方には特徴があり、表れ方によって認知症の種類や認知症の進行状況の判断ができます。また「時間や季節」→「場所」→「人間関係」と見当識障害の表れ方には順番があります。
時間見当識障害は時間がわからなくなる
まずわからなくなるのが、時間の感覚です。現在時刻がわからなくなり、長く待つことや予定に合わせて計画することができなくなっていきます。季節の移り変わりなども認識できなくなります。
場所見当識障害は場所がわからなくなる
時間見当識の次に、場所の感覚がわからなくなっていきます。方向感覚が薄れていくことで、近所でも迷子になることや自宅のトイレまで辿り着けなくなります。
人の見当識障害は人のことがわからなくなる
最後に、人の見当識障害が表れます。家族の顔や名前がわからなくなり、自分の顔も自分のものだという認識がなくなっていきます。産まれてから今までの記憶もなくなっていきます。
見当識障害の確認方法と認知症患者への接し方
見当識障害を疑う場合は、精神科・神経内科・脳神経外科などを受診しましょう。もの忘れ外来・認知症外来がある医療機関もあります。自己チェックできる方法や認知症患者への接し方はこちらです。
見当識障害を判断(評価)するためのチェックリスト
東京都福祉保健局には「自己チェックができる質問が自分でできる認知症の気づきチェックリスト」があります。チェックリストは、本人以外の家族や身近な人が代わりにチェックしても有効なので活用しやすいですね。
見当識障害の兆候を感じたら注意して接していこう
見当識の低下を感じたら、1番不安なのは本人です。まずは、ゆっくりと繰り返し話しを聞いてあげましょう。そして、大切なのは相手の自尊心を傷つけないように焦らずに感情を理解してあげることです。その上で、できるだけ一人にさせないこと、危険な物をそばに置かないように注意してください。
見当識を保つためのリハビリとは
医療現場や介護現場では、認知症の患者さんや高齢者が見当識を保つためにリハビリを行なっています。見当識を保つためのリハビリとは、どんなことをしているのでしょうか?
リアリティ・オリエンテーションと現実見当識訓練
見当識を維持する訓練のことをリアリティ・オリエンテーション、別名で現実見当識といいます。リアリティ・オリエンテーション(現実見当識)は認知症の進行を遅らせ、他者とのコミュニケーションを図ることや他者に関心を持つ効果があると言われています。
見当識障害のリハビリ方法は2種類
リアリティ・オリエンテーション(現実見当識)には、問いかけに繰り返し答えるリハビリと方法、日常の動作を通して協調性を取り戻すリハビリ方法があります。
★リアリティ・オリエンテーションの種類★
【24時間リアリティ・オリエンテーション】
日常的に行う職員と患者さんとのコミュニケーションの中で、現実の認識理解を深めるリハビリ方法です。たとえば「今は何時か」「自分の名前や年齢は」「今どこにいるのか」など日々の出来事と自分の存在意識ができるような問いを投げかけていきます。
【クラスルームリアリティ・オリエンテーション】
少人数のグループを作って定期的に集まり、プログラムに沿ってみんなで確認していくリハビリ方法です。名前や場所、時間などの情報を繰り返し伝え合い確認することで、仲間への理解やコミュニケーションの機会が増えることも期待できます。
【24時間リアリティ・オリエンテーション】
日常的に行う職員と患者さんとのコミュニケーションの中で、現実の認識理解を深めるリハビリ方法です。たとえば「今は何時か」「自分の名前や年齢は」「今どこにいるのか」など日々の出来事と自分の存在意識ができるような問いを投げかけていきます。
【クラスルームリアリティ・オリエンテーション】
少人数のグループを作って定期的に集まり、プログラムに沿ってみんなで確認していくリハビリ方法です。名前や場所、時間などの情報を繰り返し伝え合い確認することで、仲間への理解やコミュニケーションの機会が増えることも期待できます。
見当識とは?正しく理解して看護ケアに活かそう!
見当識障害は、認知症の中核症状です。今後はますます認知症患者の増加が考えられ、見当識障害の種類や表れる順番を知ることは医療現場で働く上で大切です。しっかりと理解して、今後の看護ケアに活かしていきましょう!
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.