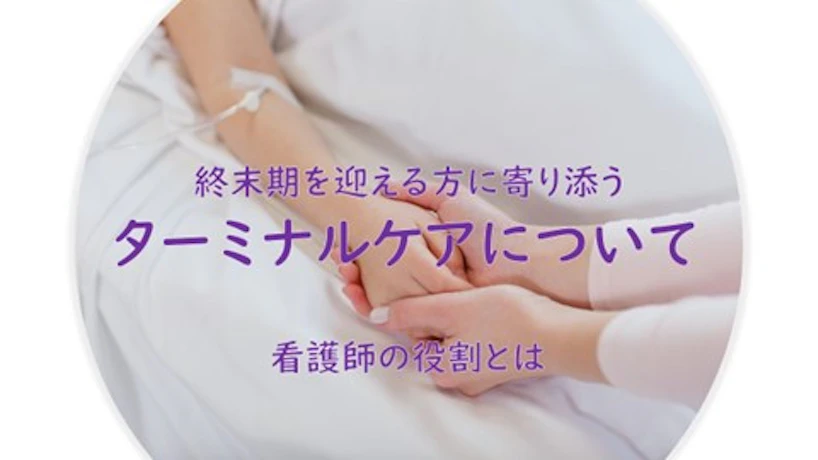仕事・スキル
公開日:2023.10.18
更新日:2023.10.24
ターミナルケアってなに?終末期を迎える患者に看護師ができることとは
#仕事内容
目次
「終末期」「ターミナルケア」「看取り」といった言葉は、近年よく耳にするワード。高齢者の割合が増えるとともに、訪問看護や介護施設などでもターミナルケアを必要とする声が高まりつつあります。
ターミナルケアとは、具体的にどのようなことをするのでしょうか。ターミナルケアの内容と看護師の役割についてお話していきます。
ターミナルケアとは、具体的にどのようなことをするのでしょうか。ターミナルケアの内容と看護師の役割についてお話していきます。
ターミナルケアとは
ターミナルケアとは、余命わずかの方をはじめ、認知症や老衰の方たちに対しておこなう医療・看護、介護ケアのことをいいます。残りの人生を少しでも心穏やかに過ごせるように痛みや不安、ストレスを緩和し患者さんのQOL(クオリティオブライフ)を保つことを目的としています。
ターミナルケア(終末期)の定義
ターミナルケアを開始するタイミングは、特定の症状がみられる場合において患者さん本人や家族の意思で治療を続行するか否かを決定します。
例えば、
などが該当します。
通常の治療とは異なり、ターミナルケアは延命を目的としていません。
できることなら患者さん本人の意思で決断できるのを理想としていますが、認知症により本人の意思確認が困難だと判断された場合、延命の決定権は患者さんの家族に委ねられることとなります。万が一、家族内で意見がまとまらなかったり、患者さんの心身の状態によりケア内容の決定が難しいと判断された場合は、医療・ケアチーム含む複数の専門家で話し合い今後の方針を決定することとなります。
【ガイドラインの一部改訂について】
平成30年には、厚生労働省の改定により一部ガイドラインが改訂されることとなりました。1つ目は、医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれるということ。
2つ目に、本人の意思が伝えられない状態となる前に、家族等の信頼できる人を前もって決めておくということ。また、患者さんが単身者の場合、信頼できる人の対象を家族から親しい友人まで拡大されます。
3つ目、心身の状態は日々変化しうるものであることから、医療・ケアの方針を繰り返し話し合うことが必要です。
さいごに、繰り返し話し合った内容は、その都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有ましょう、といった内容となっています。
例えば、
・回復の見込みがなく積極的な治療が行えなくなったとき
・老衰や認知症の場合、寝たきりで食事が取れなくなったとき
などが該当します。
通常の治療とは異なり、ターミナルケアは延命を目的としていません。
できることなら患者さん本人の意思で決断できるのを理想としていますが、認知症により本人の意思確認が困難だと判断された場合、延命の決定権は患者さんの家族に委ねられることとなります。万が一、家族内で意見がまとまらなかったり、患者さんの心身の状態によりケア内容の決定が難しいと判断された場合は、医療・ケアチーム含む複数の専門家で話し合い今後の方針を決定することとなります。
【ガイドラインの一部改訂について】
平成30年には、厚生労働省の改定により一部ガイドラインが改訂されることとなりました。1つ目は、医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれるということ。
2つ目に、本人の意思が伝えられない状態となる前に、家族等の信頼できる人を前もって決めておくということ。また、患者さんが単身者の場合、信頼できる人の対象を家族から親しい友人まで拡大されます。
3つ目、心身の状態は日々変化しうるものであることから、医療・ケアの方針を繰り返し話し合うことが必要です。
さいごに、繰り返し話し合った内容は、その都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有ましょう、といった内容となっています。
緩和ケア・ホスピスケアとの違い
「ターミナルケアと緩和ケアってどう違うの?」とふたつの違いに疑問を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
命を脅かすような病気の治療と同時進行で苦痛を和らげるためのケアを行う“緩和ケア”。対して、ターミナルケアは余命宣告をされた患者さんに苦痛の伴う治療を中止し、人間らしく死を迎えるために身の回りのサポートをおこなうことをいいます。
また、緩和ケアと同様に「ホスピスケア」というものがあります。ホスピスケアの歴史は古く、1967年にイギリス(ロンドン)で創設された施設にて末期がん患者の苦痛を取り除くためのケアを実施したことから始まります。
ホスピスの言葉の意味は、
命を脅かすような病気の治療と同時進行で苦痛を和らげるためのケアを行う“緩和ケア”。対して、ターミナルケアは余命宣告をされた患者さんに苦痛の伴う治療を中止し、人間らしく死を迎えるために身の回りのサポートをおこなうことをいいます。
また、緩和ケアと同様に「ホスピスケア」というものがあります。ホスピスケアの歴史は古く、1967年にイギリス(ロンドン)で創設された施設にて末期がん患者の苦痛を取り除くためのケアを実施したことから始まります。
ホスピスの言葉の意味は、
“H” hospitality (親切なもてなし)
“O” organized care (組織的なケア)
“S” symptom control (症状をコントロールする)
“P” psychological support (精神的な支え)
“I” individualized care (個別性の尊重)
“C” communication (コミュニケーション)
“E” education (教育)
“O” organized care (組織的なケア)
“S” symptom control (症状をコントロールする)
“P” psychological support (精神的な支え)
“I” individualized care (個別性の尊重)
“C” communication (コミュニケーション)
“E” education (教育)
となっており、身体的なケアに関わらず精神的、社会的側面も考慮し総合的にケアを行うことを指します。
緩和ケアとホスピスケアのどちらも、国内ではがん治療が必要な患者さんを対象とすることが多いですが、海外では疾患を問わず総合的にケアを行う傾向にあるようです。
緩和ケア、ホスピスケア、ターミナルケアの違い
緩和ケアとホスピスケアのどちらも、国内ではがん治療が必要な患者さんを対象とすることが多いですが、海外では疾患を問わず総合的にケアを行う傾向にあるようです。
緩和ケア、ホスピスケア、ターミナルケアの違い
緩和ケア | ホスピスケア | ターミナルケア | |
目的 | 病気の進行度は関係なく、症状による苦痛を和らげるためのサポート | 身体的、精神的、社会的側面など総合的にとらえて全人的なケアをおこなう | 本人もしくは家族の意思により延命治療を中止し、死を迎えることのサポート |
対象疾患 | 国内ではがん・エイズ治療を中心に発展している | 国内ではがん治療を中心に発展している | 疾患問わず |
年齢層 | 年齢不問 | 年齢不問 | 高齢者を対象にすることが多い |
ケアを始める時期 | 治療中~終末期まで | 治療が望めないと判断されてから終末期まで | 治療が望めないと判断されてから終末期まで |
ターミナルケアをおこなう施設
ターミナルケアを実施しているのは、一般病棟やホスピス・緩和ケア病院や緩和ケア外来、訪問看護、自宅、介護施設にいたるまで多くの場所で取り入れられています。
しかし、一般病棟では重症患者を優先してしまうことから病院によってはターミナルケアを希望する方のために緩和ケアチームを配置するところもあります。
ほかにも診療科の場合ですと、消化器疾患、呼吸器疾患などは患者さんの割合が多く、産婦人科、小児科、泌尿器科においてもターミナルケアを必要とする方は少なからずいます。
近年では、家族に見守られながら終末期を迎えたいと希望する方が増える一方で、核家族の増加による家族関係の希薄により介護施設や自宅での看取りはまだまだ少ない傾向にあります。病院で心穏やかに終末期を迎えるためには、医療スタッフの献身的なケアが重要となってくるのです。
しかし、一般病棟では重症患者を優先してしまうことから病院によってはターミナルケアを希望する方のために緩和ケアチームを配置するところもあります。
ほかにも診療科の場合ですと、消化器疾患、呼吸器疾患などは患者さんの割合が多く、産婦人科、小児科、泌尿器科においてもターミナルケアを必要とする方は少なからずいます。
近年では、家族に見守られながら終末期を迎えたいと希望する方が増える一方で、核家族の増加による家族関係の希薄により介護施設や自宅での看取りはまだまだ少ない傾向にあります。病院で心穏やかに終末期を迎えるためには、医療スタッフの献身的なケアが重要となってくるのです。
ターミナルケアの内容
では、ターミナルケアについて具体的にどのようなケアをおこなっているのでしょうか。
大きく分類して、「身体的ケア」「精神的ケア」「社会的ケア」の3つにわかれます。順にみていきましょう。
大きく分類して、「身体的ケア」「精神的ケア」「社会的ケア」の3つにわかれます。順にみていきましょう。
身体的ケア
身体的ケアとは、薬や点滴などを投与し、痛みや辛さを緩和するケアのこと。
末期がんをはじめ、病気の終末期には症状や治療方法により強い痛みが生じてしまいます。普段、身動きが取れない寝たきりの患者さんの身体的苦痛を少しでも和らげるために看護師は身の回りのケアを行います。
例えば、
などがあります。
ほかにも、食事ができなくなったとき、食べやすいように料理を細かくする、場合によってはチューブを通した経管栄養、胃ろうといった処置をおこない栄養補給をします。
しかし、栄養補給は延命処置にあたる行為でもありますので、実施するかどうかは本人または家族の意思を確認しなければなりません。
末期がんをはじめ、病気の終末期には症状や治療方法により強い痛みが生じてしまいます。普段、身動きが取れない寝たきりの患者さんの身体的苦痛を少しでも和らげるために看護師は身の回りのケアを行います。
例えば、
・からだを清拭し身だしなみを整える
・定期的に体の向きを変えて褥瘡(床ずれ)を防止する
・酸素吸入、点滴投与
などがあります。
ほかにも、食事ができなくなったとき、食べやすいように料理を細かくする、場合によってはチューブを通した経管栄養、胃ろうといった処置をおこない栄養補給をします。
しかし、栄養補給は延命処置にあたる行為でもありますので、実施するかどうかは本人または家族の意思を確認しなければなりません。
精神的ケア
患者さんの不安や恐怖、ストレスを取り除き心穏やかに過ごしてもらうためのケアです。
日常的に看護師から患者さんとコミュニケーションをとることにより不安や恐怖を和らえることができます。また、限られた時間を家族や友人と楽しく過ごすための配慮も必要です。このケアは看護師や家族以外にも、ボランティアの方が援助してくれることもあります。
日常的に看護師から患者さんとコミュニケーションをとることにより不安や恐怖を和らえることができます。また、限られた時間を家族や友人と楽しく過ごすための配慮も必要です。このケアは看護師や家族以外にも、ボランティアの方が援助してくれることもあります。
社会的ケア
ターミナルケアをおこなううえで、問題になりやすいのが費用についてです。
終末期を迎えると、患者さん自身に係るケアだけでなく、費用や関係者各所とのやりとり、手続きなど家族にかかる負担は大きくなります。介護や看護のストレス、社会との関わり・特に福祉制度を使用する際、家族の負担を減らす手助けをするのもターミナルケアの仕事のひとつ。
ケアマネージャーと連携を取りつつ、家族の話や悩みを聞いたり、支援制度の紹介、情報を提供したりと、さまざまな支援をおこなう必要があります。
終末期を迎えると、患者さん自身に係るケアだけでなく、費用や関係者各所とのやりとり、手続きなど家族にかかる負担は大きくなります。介護や看護のストレス、社会との関わり・特に福祉制度を使用する際、家族の負担を減らす手助けをするのもターミナルケアの仕事のひとつ。
ケアマネージャーと連携を取りつつ、家族の話や悩みを聞いたり、支援制度の紹介、情報を提供したりと、さまざまな支援をおこなう必要があります。
看護師の役割
3つのケアをさまざまな医療スタッフが連携をとり、患者さんに苦痛なく終末期を迎えてもらうためのターミナルケア。 そのなかで、おもに看護師の役割は以下のようなものが挙げられます。
・患者さんを理解し尊重した支援をする
・患者さんやその家族の心のケアをする
・プライバシー保護などの倫理的配慮
・疾患や症状に対する正しい知識とスキルをもつ
ターミナルケアにおいてもっとも重要となってくるのが、“患者さんと家族の意思を尊重する”ということ。延命治療を続けるか中止するかの判断は、病院側の意見だけでは決めことができません。患者さんの症状、意思や境遇、家族の有無などは人によって異なります。
看護師でも対応に困ることも多いため、その際にはガイドライン(※)に沿ってケアを進めるようになります。
・患者さんを理解し尊重した支援をする
・患者さんやその家族の心のケアをする
・プライバシー保護などの倫理的配慮
・疾患や症状に対する正しい知識とスキルをもつ
ターミナルケアにおいてもっとも重要となってくるのが、“患者さんと家族の意思を尊重する”ということ。延命治療を続けるか中止するかの判断は、病院側の意見だけでは決めことができません。患者さんの症状、意思や境遇、家族の有無などは人によって異なります。
看護師でも対応に困ることも多いため、その際にはガイドライン(※)に沿ってケアを進めるようになります。
家族(遺族)への配慮
ターミナルケアは、患者さんのケアだけでなくその家族のサポートも欠かしてはいけません。大切な人の死に直面するということは精神的不安定も大きく、亡くなることのショックや先々の生活に関する不安を少しでも取り除くことを心がけてください。
医師や看護師ができることは、患者さんの今の状態を明確に説明し、面会時以外の様子や今後予想される事柄を適宜丁寧に伝えるということ。伝えるタイミングは家族の精神状態を考慮したうえで、慎重に対応しましょう。
また限られた時間のなかで悔いなく過ごせるように、患者さんと家族のあいだに入り、両者の関係を取り持つことが大切です。それぞれの思いを受け止めて双方が十分な時間を共有できるようにサポートしていきましょう。
もちろん、患者さんの死後も家族が穏やかに日々の生活を過ごせるように「ご家族に見守られて○○さんも安心されていましたね。お疲れ様でした。」と、これまでの家族の心労や支援を肯定してあげることが大切です。
医師や看護師ができることは、患者さんの今の状態を明確に説明し、面会時以外の様子や今後予想される事柄を適宜丁寧に伝えるということ。伝えるタイミングは家族の精神状態を考慮したうえで、慎重に対応しましょう。
また限られた時間のなかで悔いなく過ごせるように、患者さんと家族のあいだに入り、両者の関係を取り持つことが大切です。それぞれの思いを受け止めて双方が十分な時間を共有できるようにサポートしていきましょう。
もちろん、患者さんの死後も家族が穏やかに日々の生活を過ごせるように「ご家族に見守られて○○さんも安心されていましたね。お疲れ様でした。」と、これまでの家族の心労や支援を肯定してあげることが大切です。
終末期における感情のコントロール
眠るように安らかな最期を迎える方、闘病の末に亡くなられる方と患者さんがどんな終末期を迎えるかは十人十色です。これまで行ってきた日々の看護、ご家族の心労を考えると 「ああしたらよかった」「こうしたほうがよかった」と後悔の念を引きずることは必ずあるでしょう。看取りは、経験を積んだ看護師であっても決して慣れるものではありません。
大切なのは、慣れるのではなく、受け入れるということです。
「その人らしい死を迎えるためにできることはなにか」
「患者さんの死から自分は何を学んだのか」
そんなことを考えながら死と向き合い、日々葛藤し向上する心を持つようにしましょう。
大切なのは、慣れるのではなく、受け入れるということです。
「その人らしい死を迎えるためにできることはなにか」
「患者さんの死から自分は何を学んだのか」
そんなことを考えながら死と向き合い、日々葛藤し向上する心を持つようにしましょう。
さいごに
患者さんやその家族にとって終末期は家族で過ごす最期の時間です。患者さんやその周囲の方々、もちろん看護師自身にとっても悔いのないように、自分にできることは何かを常に考え続ける必要があります。
誰しも必ず死は訪れます。必ず訪れるものだからこそ、その人が望む理想の形となるように、医師や看護師は早めに予測して終末期を迎えるための体制を整えてあげることが大切なのです。
誰しも必ず死は訪れます。必ず訪れるものだからこそ、その人が望む理想の形となるように、医師や看護師は早めに予測して終末期を迎えるための体制を整えてあげることが大切なのです。
#仕事内容
関連コラム
© TRYT Career ,Inc.